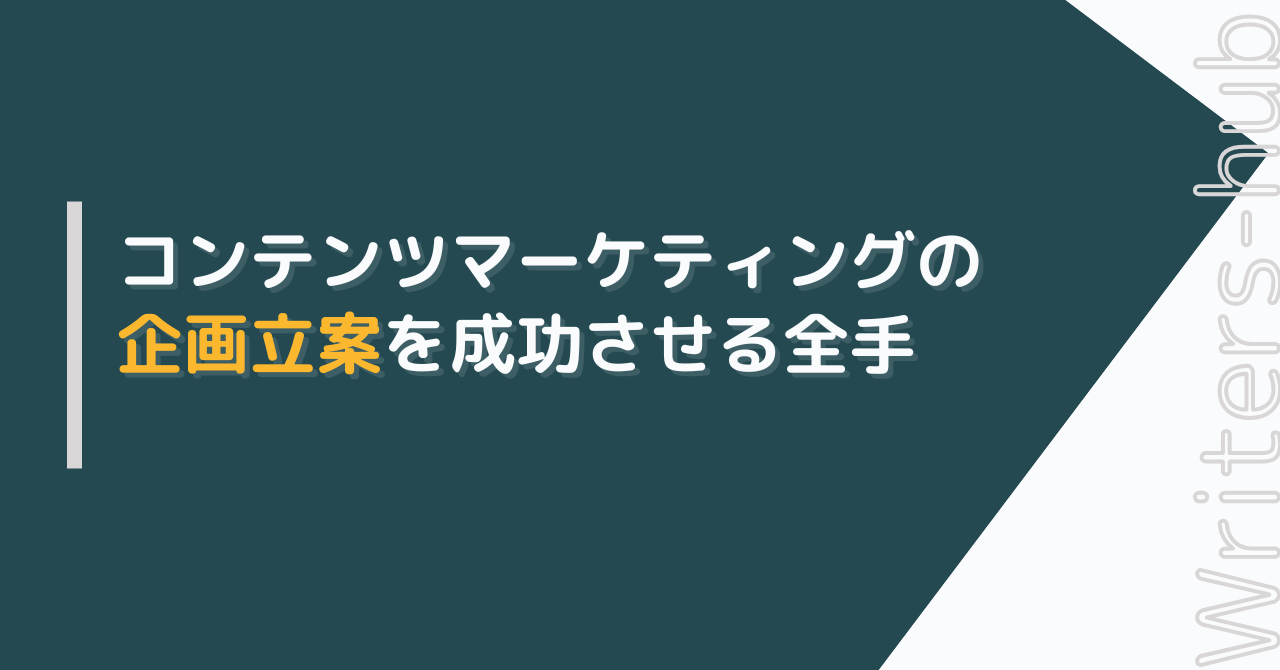
成功するコンテンツマーケティングの企画立案の作り方|企画書を作る際のポイントも
コンテンツマーケティングを導入する際、もっとも重要になるのは企画立案です。明確な狙いや優先順位を決めずに始めると、方向性があいまいになり、社内調整が難しくなります。さらに、どのようにコンテンツを制作し運用するかが定まっていない場合は、効果測定もままなりません。
本記事では、コンテンツマーケティングの企画立案が成功するための手順を具体的に解説します。戦略設計からコンテンツ案の策定方法、さらには推進する際のスケジュールや組織体制もわかるようにまとめました。社内プレゼン用の企画書や提案書を作る際にも参考にしてください。
あわせて、コンテンツマーケティングの具体的なメリットや運用フローの事例も紹介します。最後には中長期的な成果を実現するためのコツや注意点を述べますので、初めて企画立案を行う方や運用がうまくいかない方はぜひ最後までご覧ください。
『SEO最強』AIライティングツールで記事を量産したい人は他にいませんか?
3000記事以上の執筆・編集経験を持つSEO専門ライターが、2年間の試行錯誤の末に開発した革新的AIシステム。
- キーワードを入力するだけで5万字超のプロンプトが生成
- ClaudeやChatGPTにコピペするだけで装飾済みの原稿が一発完成
- ライター外注費を最大90%削減可能
-------------------
![]() こんな課題を抱えていませんか?
こんな課題を抱えていませんか?
- 「コンテンツ制作費、もっと安くならないの?」と言われ失注が増えてきた
- ライターとのコミュニケーションコストや管理が大変
- いくらAIツールを試しても本当に「自分が書かなくていいレベル」にならない
-------------------
「一気通貫Pro」があれば解決します!
「立ち上げ4ヶ月で4万PV達成!(上場企業)」
「外注費を90%削減できた。一気通貫Proの原稿が良すぎて6割は時間削減できている(Web制作会社)」
「低コストのSEO記事制作プランを自信を持って提案できるようになり受注率が向上(制作会社)」
他のAIツールとの決定的な違いはこの3点!
- システム会社やSEO会社ではなく現役ライターが開発したから、プロが書いたような「使える」原稿が出力される
- プロンプトを出力するツールなので、生成AIに「ここをもっとこうして」と追加指示で修正も簡単(他のAIツールは修正は人力)
- 生成AIのプランに準じて事実上無制限に記事作成可能(他の多くは月間制限あり)
-------------------
![]() 30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
AIの出力そのままの無料デモ記事の作成も承っています。まずは実際の出力をご確認ください!
コンテンツマーケティングの企画立案とは
まず「コンテンツマーケティングの企画立案」とは何を指すのでしょうか。商品の販売やサービス認知度の向上を目指すために、以下のような要素を総合的に検討してプランを作成する作業です。
- 目的とKGI/KPIを設定する
- ペルソナを定義する
- コンテンツのテーマや形式、発信チャネルを検討する
- 必要な体制、リソース、スケジュールを決める
- 運用後の効果検証と改善サイクルを明確にする
とくにコンテンツマーケティングは比較的長期間の運用が必要となるため、あらかじめ視覚化されたプラン(フロー)や提案書を用意して、社内外の関係者を巻き込みながら実行することが大切です。
体制構築やターゲット設定に時間をかけたくない企業ほど、最初の企画立案をしっかり行うことが重要です。安易に記事制作や動画制作を始めてしまうと、想定外のコストやリソース不足に苦しむ可能性があるため注意が必要です。
企画立案のメリットと押さえておきたい前提
コンテンツマーケティングの企画立案を実施すると、多くのメリットが得られます。同時に、前提として理解しておくべきことも存在します。以下ではメリットと前提条件を概説します。
企画立案のメリット
メリット1. 投資対効果を算出しやすい
企画の段階でKGI(最終目標)やKPI(重要評価指標)を明文化すると、事前に期待値を可視化できます。将来的にどれくらいの成果を目指すか、どんなスケジュールで投資回収を図るかが分かるため、社内プレゼン時の説得力も高まるでしょう。
メリット2. 他部署の協力が得やすい
他の施策との違いや優先度を説明できるようになり、ステークホルダーや関連部署との連携がしやすくなります。例えばコンテンツマーケティングとリスティング広告の違いを正しく理解させることで、予算配分やスケジュール調整がスムーズに進む場合があります。
メリット3. 進行トラブルを未然に防止できる
運用フローや必要なリソースを洗い出しておけば、誰がどのタイミングで何をするかが明確になります。運用途中のタスク漏れや工数オーバーを抑えるうえでも企画書は有用です。
押さえておきたい前提
ただし、コンテンツマーケティングは短期的な成果を狙う手法ではありません。数週間や1か月で結果が出る広告施策ではなく、内容を作り込み、継続的に更新しながら見込み客との接点を育てるアプローチです。
そのためコンテンツマーケティングの導入では「少なくとも半年から1年程度の期間」が前提となります。リード育成を想定しているBtoB企業では、さらに長い期間を要するケースもあります。短期決戦向けの施策とは異なるという認識を事前に共有しておくことが重要です。
成功する企画立案の8ステップ
ここからは、コンテンツマーケティングの企画立案を具体的に進めるための8ステップを紹介します。それぞれのステップで意識すべきポイントを押さえましょう。
- 現状分析
- 目的とKPI設定
- ペルソナ策定
- カスタマージャーニーマップ作成
- コンテンツ企画の発案
- 運用体制とリソースを確認
- 制作・運用フローの設定
- 効果測定の手順を組み込む
1. 現状分析
まず自社と競合を取り巻く状況を分析します。自社サイトがどれくらいのトラフィックや検索順位を獲得しているか、競合はどのようなコンテンツ戦略を実施しているかを調べる段階です。
SWOT分析や3C分析などのフレームワークを用いれば、客観的に現状を評価できます。現状分析で得たデータは、企画書に具体的な裏付けを与えてくれます。
2. 目的とKPI設定
続いて、コンテンツマーケティングを行う目的とKPIを定めます。目的は企業によって異なりますが、下記のような例が考えられます。
・見込み客を獲得してWeb経由の売上を上げたい
・自社の専門性を示して認知度を高めたい
・ブランドを強化して優秀な人材を採用したい
KPIは測定可能であることが必須です。期間ごとの流入数や問い合わせ数、CVRなど、定量的に追える指標を用いて達成度を評価します。
3. ペルソナ策定
コンテンツマーケティングではターゲットを詳細にイメージできるペルソナを作成すると、コンテンツの方向性がブレにくくなります。
たとえばBtoB向け製品であれば役職・業種・企業規模、導入の意思決定範囲などを細かく設定します。BtoC向けなら性別・年代・趣味・年収・家族構成などが着眼点になるでしょう。
ペルソナ策定が甘いと、コンテンツのテーマが散漫になりがちです。後工程のカスタマージャーニーマップ作成やコンテンツ企画の質を高めるうえでも、丁寧な設定が欠かせません。
4. カスタマージャーニーマップ作成
ペルソナの購買行動を時系列で把握するのが、カスタマージャーニーマップです。認知期から検討期、比較期、最終判断期といった流れのなかで、どのような心理状況や疑問点が発生しているのかを可視化します。
ジャーニーマップを作成すると、各段階においてユーザーが求める情報が異なることがはっきりします。認知期には気づきの情報(そもそも何が問題なのか)を提供し、検討期には製品比較のための具体的データを提示するといった施策が明確になるでしょう。
5. コンテンツ企画の発案
ここで「どのようなコンテンツをどんなタイミングで発信するか」を立案します。記事、動画、ホワイトペーパー、SNS、メールマガジンなど、ペルソナやジャーニーに合わせて最適なフォーマットを選定してください。
また、具体的なコンテンツテーマを洗い出して、ひとつずつ優先度を定めます。検索キーワード(「コンテンツマーケティング 企画書」「コンテンツマーケティング 戦略」「コンテンツ企画 例」など)の検索ボリュームと競合ページの内容を確認し、勝算があるものから着手するのが定石です。
6. 運用体制とリソースを確認
企画立案だけではなく、運用フェーズに必要な体制も早めに整えます。どの部署がライティングを担当するのか、外部パートナーを活用するのか、予算や人件費はどう配分するかなどを検討し、可能ならば周囲の理解を得ておくことが理想的です。
運用体制が曖昧なまま制作を始めると、担当者の業務負担が過度に増えるケースがあります。企画立案の段階でリソースを明確にしておきましょう。
7. 制作・運用フローの設定
コンテンツを制作し公開するまでの流れを定義します。たとえば以下のようなステップを順番に設定するとイメージしやすくなります。
・キーワード選定やターゲットの設定
・一次情報(取材や調査)や参考データの収集
・仮タイトルと構成案の作成
・ライティング
・レビューや校正
・公開後の効果測定
また、SaaS系企業など長期的なコンテンツ量産が必要な場合は月次や週次で記事をどれだけ公開するかを計画的に決めておきましょう。
8. 効果測定の手順を組み込む
最後は効果測定の方法とスケジュールを明記します。コンテンツマーケティングは検索順位、アクセス数、問い合わせ数、CVR、リード獲得数など、多様な指標で効果を確認できます。Googleアナリティクスやサーチコンソールを利用するだけではなく、HubSpotやMAツールを活用するケースもあります。
効果測定で得られた知見を元に、次のPDCAを回す仕組みを設計することが重要です。KPI未達成の場合の修正案やリライト基準を企画書に含めておくとよいでしょう。
企画立案時に押さえるべきポイント
成功するためには、以下のポイントを意識してください。どれもよくあるつまずきポイントでもあり、あらかじめ検討しておくことで余計なトラブルを回避できるでしょう。
社内稟議を通しやすくする具体策
コンテンツマーケティングは中長期の施策であるがゆえ、すぐにROIが見えにくいことがあります。上層部への提案には数字と事例を添えましょう。
例えば競合がコンテンツマーケティングを活用している事例を提示したり、簡易的なROIを試算したグラフを見せたりすることで、経営層からの信頼を得やすくなります。
また、コンテンツマーケティングは広告費が抑えやすい点や、潜在顧客にもアプローチしやすい点を強調すると、社内稟議が通りやすくなるでしょう。
ステークホルダーごとの不安を解消する
営業部署なら「顧客に響く内容になっているのか」、開発担当なら「専門的な説明が不十分ではないか」、経営陣なら「投資に見合う売上が本当に期待できるか」など、不安はさまざまです。
あらかじめ想定される質問や不安要素をリストアップし、企画書で裏付けを示します。運用フローだけではなく、どのようなリードナーチャリング施策を組み込むかを示すのも効果的です。
外部パートナーとの連携
コンテンツ制作をすべて内製化する企業も増えていますが、リソースが足りない場合や専門性が不足する場合は外部の支援を活用すると効率的です。例えば、記事執筆だけを外注し、テーマや企画管理は社内担当者が担う方法があります。
動画やWebサイト制作など幅広い範囲で外部パートナーと協業する場合は、ディレクションフローや成果物のクオリティチェック体制を明確にしておきましょう。
具体例: 企画立案フローを図解
簡単な図解を用いて、企画立案フローのイメージを示します。流れを可視化すると、プロジェクトメンバー同士の認識が合いやすくなります。
以下の一例はあくまでシンプルなモデルですが、社内説明資料などに組み込む際は部門別の役割分担やスケジュールを加えるとより具体的です。
1.現状分析
2.目的/KPI設定
3.ペルソナ策定
4.企画
5.運用体制
6.制作フロー
7.効果測定
上記のように順序立てて検討すれば、コンテンツマーケティング全体の流れが把握しやすくなります。企画書には「誰が」「いつ」「どのフェーズ」を担当するかも付け加えてください。
運用開始後に起きやすい失敗例と解決策
ここからは運用開始後によくある失敗例を紹介します。あらかじめ想定しておくことで、企画立案の段階から解決策を盛り込めます。
リソース不足で更新が滞る
コンテンツ数を増やし続けないと成果が見えにくいにもかかわらず、想定以上にライティングや取材に時間を取られるケースがあります。結果として記事更新が止まってしまう事態も珍しくありません。
リソース不足を回避するためには、外注やAIライティングツールを適宜活用することが効果的です。企画書に「どのタイミングで外部委託するか」「どの業務を社内で担うか」を事前に盛り込んでおきましょう。
KPIが明確でないため効果測定できない
「なぜこのコンテンツを制作するのか」「どの指標をどの期間で見ていくのか」があいまいなまま運用してしまい、実績を正しく評価できない事例です。最初の企画立案時点でKPIを設定しておきましょう。途中でKPIが不十分であると気づいた場合は、柔軟に更新してください。
競合の追随やトレンド変化への対応が遅れる
運用フェーズで定期的に競合サイトをチェックしないと、新しいテーマやキーワードを先行して取られたり、検索エンジンのアルゴリズム変更に乗り遅れたりする場合があります。適度な頻度でリサーチを行い、記事をリライトする仕組みを企画書に含めておくことが大切です。
成功事例: BtoB SaaS企業のコンテンツマーケティング
ここでは一例として、BtoBのSaaS企業がコンテンツマーケティングを導入し、成果を上げた事例を簡単に紹介します。実際の企画書でどのような考え方が反映されるかをイメージしやすくなるでしょう。
企業概要:
・クラウド型営業支援ツールを開発
・リード獲得と商談数増加が主な狙い
実施施策:
・「クラウド営業支援」「営業DX」などの検索キーワードを中心に記事を量産
・製品の機能紹介だけでなく、営業改革ノウハウや具体的事例を積極発信
・運用フローをあらかじめ週次ベースで設定し、公開スケジュールを厳守
・HubSpotを導入して行動データをトラッキングしながら、見込み客に適切なメールやホワイトペーパーを配信
成果:
・6か月後に対象キーワードで上位表示し始める
・月間1万PV以上の流入を獲得
・問い合わせ件数が2倍に増加し、営業がアプローチ可能なリードも増えた
このように、コンテンツ企画と運用フローをあらかじめ具体化しておけば、限られたリソースでも効率よく実行できます。BtoBの場合は問い合わせから商談までの期間が長くなる傾向があるため、メールやイベントなど他の施策とも連携して成果を最大化することが鍵です。
コンテンツマーケティングの企画書を作る際のポイント
最後に、企画書を作る際に押さえておくべき要点をまとめます。社内合意形成をスムーズに進めるだけでなく、今後の運用フェーズで迷いを減らす効果もあります。
背景とゴールを明確にする
企画書には、「なぜコンテンツマーケティングが必要なのか」という背景と、運用を通じて達成したいゴールをはっきり記載してください。特に経営陣や上司にプレゼンする場合、現状の課題と目指す姿をセットで示すと説得力が増します。
具体的なリソース計画を提示する
運用に必要な人的リソース、外部委託費用、ツール導入費などを見積もり、具体的なコストを示します。「いつ、どの部署が、どれだけの時間を割く必要があるか」という説明があると承認を得やすくなります。
スケジュールとロードマップを示す
中長期にわたる施策であることを踏まえ、最低半年から1年程度のスケジュールを企画書に含めましょう。月ごとの目標記事数や、アクセス数の段階的な目標などを設定しておくと、進捗管理が容易になります。
まとめ: 企画立案と運用が合致するとコンテンツは強力な資産になる
コンテンツマーケティングの企画立案は、運用段階での混乱や成果不足を防ぐために重要なプロセスです。目的と目標の設定、ペルソナ策定、コンテンツの種類やテーマ選定、運用体制・リソースの確認、効果測定の仕組みなど、あらゆる要素を総合的に検討しなければなりません。
記事や動画などのコンテンツは一度制作すれば自社の強力な資産になります。長期的に育てながら検索流入や見込み客獲得を狙う施策として、コンテンツマーケティングを活用してください。
コンテンツマーケティングの企画立案なら合同会社Writers-hubに相談を
コンテンツマーケティングにはさまざまなノウハウが必要です。どのキーワードで記事を作成するか、どのように見込み客を育成するかなど、細部まで戦略を練り上げなければ成果にはつながりません。
合同会社Writers-hubは、SEO記事コンテンツ作成やSEOキーワード戦略設計、そして社内へのノウハウ定着を実現する内製化支援を行っています。具体的には、以下のようなサービスが可能です。
1. SEO記事コンテンツ作成
経験豊富なライター陣が検索上位を狙える記事を執筆し、自然な導線で自社サービスの訴求を行います。独自ツールで構成を作り込み、公開後の効果検証やリライト提案もサポートいたします。
2. SEOキーワード戦略設計
サイト全体のキーワードマップを設計し、どの記事から優先的に作成すべきかを定量的に示します。競合分析や市場動向を踏まえた上で、内部リンクの構造までもれなく提案します。
3. SEO記事内製化支援
自社で記事を作りたい企業向けに、ライティング手法や生成AI活用方法を伝授します。編集フローやチェック体制の構築も含めてサポートし、長期的に質の高いコンテンツを供給できる体制を作り上げます。
このほか、課題訴求型のWebサイト制作や各種セミナーにも対応しています。自社の強みを最大限に生かすコンテンツマーケティングの企画立案がしたいと感じている場合は、ぜひ下記よりお問い合わせください。
コンテンツマーケティングは長期的な成果が期待できる一方で、一定の知見と運用体制が必要です。適切なパートナー選びによって、より早く確実に結果を出すことが可能になります。ぜひ一度、プロ視点でのアドバイスをご検討ください。


