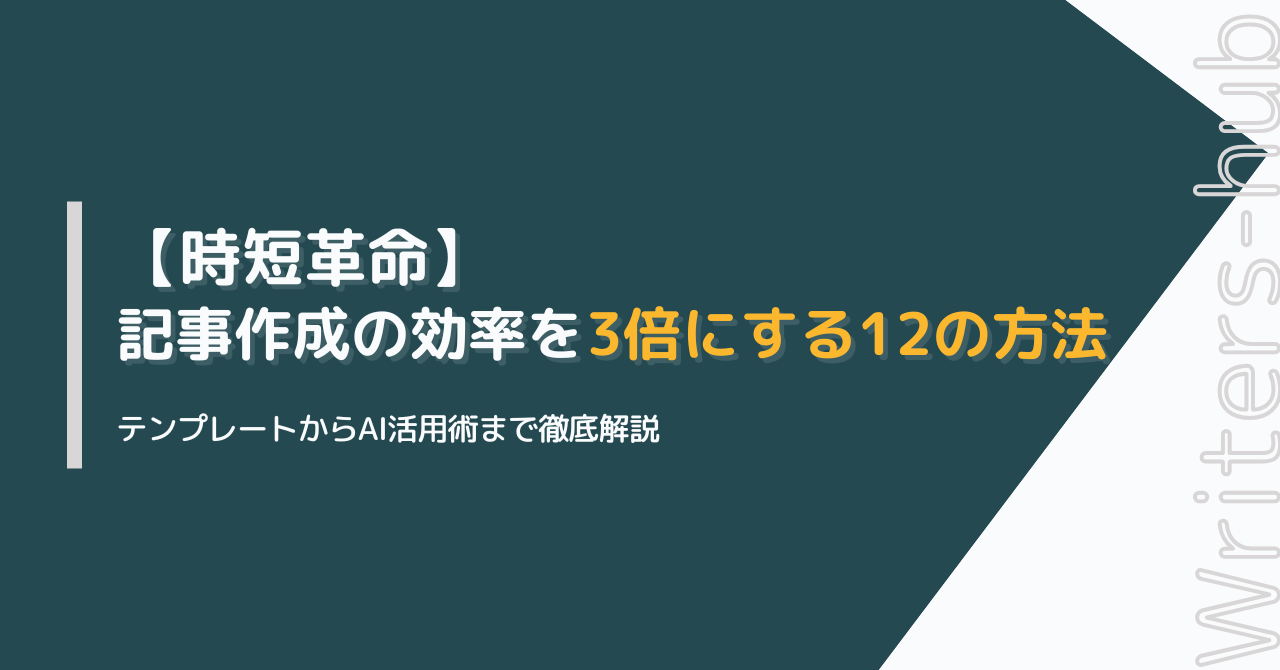
記事作成の効率を3倍にする12の方法|テンプレートからAI活用術まで徹底解説
ブログ記事やコンテンツマーケティングを行う企業担当者にとって、記事作成の「時間」は常に課題となっています。ネタ出しから構成、執筆、校正、公開までの一連のプロセスに多くの時間を要し、思うように更新頻度を維持できないケースも少なくありません。
特に最近では、ChatGPTなど生成AIの登場により記事作成の手法も大きく変化しています。こうした最新ツールを活用すれば、これまでよりも効率的に質の高い記事を生み出すことが可能です。
本記事では、記事作成の時間を大幅に短縮する具体的な12の方法と、記事の質を維持したままスピードアップするためのテクニックを解説します。テンプレートの活用からAIツールの使い方まで、現場ですぐに実践できる内容を詳しく紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
『SEO最強』AIライティングツールで記事を量産したい人は他にいませんか?
3000記事以上の執筆・編集経験を持つSEO専門ライターが、2年間の試行錯誤の末に開発した革新的AIシステム。
- キーワードを入力するだけで5万字超のプロンプトが生成
- ClaudeやChatGPTにコピペするだけで装飾済みの原稿が一発完成
- ライター外注費を最大90%削減可能
-------------------
![]() こんな課題を抱えていませんか?
こんな課題を抱えていませんか?
- 「コンテンツ制作費、もっと安くならないの?」と言われ失注が増えてきた
- ライターとのコミュニケーションコストや管理が大変
- いくらAIツールを試しても本当に「自分が書かなくていいレベル」にならない
-------------------
「一気通貫Pro」があれば解決します!
「立ち上げ4ヶ月で4万PV達成!(上場企業)」
「外注費を90%削減できた。一気通貫Proの原稿が良すぎて6割は時間削減できている(Web制作会社)」
「低コストのSEO記事制作プランを自信を持って提案できるようになり受注率が向上(制作会社)」
他のAIツールとの決定的な違いはこの3点!
- システム会社やSEO会社ではなく現役ライターが開発したから、プロが書いたような「使える」原稿が出力される
- プロンプトを出力するツールなので、生成AIに「ここをもっとこうして」と追加指示で修正も簡単(他のAIツールは修正は人力)
- 生成AIのプランに準じて事実上無制限に記事作成可能(他の多くは月間制限あり)
-------------------
![]() 30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
AIの出力そのままの無料デモ記事の作成も承っています。まずは実際の出力をご確認ください!
なぜ記事作成に時間がかかるのか?
記事作成において時間がかかる原因は主に以下の5つです。まずはこれらを理解し、どこに効率化の余地があるのかを把握しましょう。
- 明確なプロセスやテンプレートがなく、毎回一から構成を考えている
- 情報収集と整理に時間がかかっている
- 執筆途中で方向性がブレて書き直しが発生する
- 完璧主義で校正・修正を繰り返してしまう
- タイピングや文章作成そのものに時間がかかる
これらの課題を解決するには、記事作成の各工程を体系化し、効率的なワークフローを確立することが重要です。一つひとつのステップに明確な時間配分を設け、必要十分な品質を確保しながら、不要な作業を省いていくことで、記事作成の時間を大幅に短縮できます。
記事作成を効率化する12の方法
1. 記事テンプレートを活用する
記事作成の最大の時短ポイントは、テンプレートの活用です。ゼロから記事構成を考えるのではなく、あらかじめ定型フォーマットを用意しておくことで、執筆の迷いを大幅に減らすことができます。
テンプレートを使うことで、記事の一貫性が保たれるだけでなく、読者にとっても情報が整理されて理解しやすくなります。また、SEO的にも見出し構造が最適化され、検索エンジンからの評価も安定します。
下記は基本的なブログ記事のテンプレート例です。これをカスタマイズして自分専用のテンプレートを作りましょう。
| 基本的なブログ記事テンプレート |
| 【導入部】 ・読者の課題や悩みに共感 ・記事で解決できる内容の予告 ・信頼性を示す要素(経験や実績など) |
| 【本論】 ・H2見出し:テーマに関する基本知識 ・H2見出し:具体的な解決方法(複数のH3で展開) ・H2見出し:実践するためのステップ ・H2見出し:よくある質問や注意点 |
| 【結論】 ・内容のまとめ ・読者へのアクションの提案 ・(必要に応じて)自社サービスの紹介 |
2. キーワード設計を事前に行う
SEOを意識した記事作成では、事前のキーワード設計が執筆効率を大きく左右します。ターゲットキーワードを決めてから記事を書き始めることで、内容がブレにくくなり、後からの大幅な修正が必要なくなります。
キーワード設計のポイントは以下の通りです:
- メインキーワード1つと関連キーワード3〜5つを選定
- キーワードの検索意図(ユーザーの目的)を明確にする
- 競合上位記事が獲得している関連キーワードをチェック
- H1、H2見出しにメインキーワードを含める
無料ツールの「ラッコキーワード」や「Ubersuggest」などを活用して、効率的にキーワード調査を行いましょう。事前に準備することで、執筆中に「このキーワードも入れるべきか」といった迷いがなくなります。
3. 構成は箇条書きから始める
記事の構成作りは最初から完璧な文章を書こうとせず、箇条書きから始めるのが効率的です。まずはH2、H3見出しを決め、各セクションで伝えたいポイントを箇条書きでリストアップします。
この方法のメリットは:
- 全体像が早い段階で把握できる
- 論理的な流れを先に確認できる
- 不足している情報が明確になる
- 執筆の心理的ハードルが下がる
箇条書きの構成さえ完成すれば、あとは各ポイントを文章化していくだけなので、執筆スピードが格段に上がります。これは「アウトライン執筆法」と呼ばれる手法で、プロのライターも多く実践しています。
4. 音声入力を活用する
タイピングが苦手な方や、思考を止めずに文章を生み出したい方には、音声入力が強力な時短ツールになります。スマートフォンの音声入力機能やGoogle Docの音声入力を活用すれば、タイピングよりも格段に速く文章を入力できます。
音声入力の活用方法:
- 静かな環境で、明瞭に話す
- 句読点も「てん」「まる」と声に出して入力
- 先に構成を決めておき、セクションごとに話す
- 後から編集することを前提に、文法や言い回しを気にしすぎない
音声入力は特に初稿の作成に有効です。思考の流れに合わせて話すだけで文章が生まれるため、いわゆる「書き出しの壁」を乗り越えやすくなります。
5. Googleスプレッドシートでコンテンツ管理
記事作成を効率化するには、記事のアイデアから進捗管理までをGoogleスプレッドシートで一元管理することが効果的です。複数の記事を並行して進める場合や、チームで作業する場合に特に役立ちます。
スプレッドシートに含めるべき項目:
- 記事タイトル案
- ターゲットキーワード
- 記事の目的・ゴール
- 主な見出し構成
- 参考URL・情報源
- 進捗状況(構成中/執筆中/校正中/公開済み)
- 担当者
- 期限
このようにコンテンツを管理することで、「次に何を書くべきか」という意思決定の時間を削減でき、執筆に集中できる環境が整います。また、過去に書いた記事の振り返りも容易になり、内部リンクの設計にも役立ちます。
6. AIツールを活用する
現在の記事作成において、AIツールの活用は最も効果的な時短手段の一つです。特にChatGPT、Perplexity.AI、Bing AI(Copilot)などは、情報収集から文章生成まで様々な場面で力を発揮します。
AIツールの効果的な活用方法:
| ツール名 | 主な活用場面 | 使い方のポイント |
| Perplexity.AI | 情報収集・最新情報の確認・構成案作成 | 具体的な質問をする・複数ソースからの情報を統合する |
| Bing AI(Copilot) | 下書き生成・見出し提案・リライト | 「作成」モードを使う・トーンや長さを指定する |
| ChatGPT | アイデア出し・文章作成・校正 | 詳細な指示を与える・出力結果を編集する |
AIツールを使う際の重要なポイントは、「丸投げ」ではなく「協働ツール」として活用することです。AIの出力をそのまま使うのではなく、構成案や下書きとして活用し、自分の専門知識や経験を加えて編集することで、オリジナリティのある記事に仕上げましょう。
7. 作業環境を整える
効率的に記事を作成するには、集中できる作業環境を整えることも重要なポイントです。以下の点に注意して、執筆に集中できる環境を作りましょう。
- 通知をオフにする(メール、SNS、メッセージなど)
- 集中タイマーを使う(ポモドーロ・テクニック:25分作業→5分休憩)
- 作業に必要なツールだけを開く
- 適切な照明と椅子の高さを確保する
- 集中できる音楽やホワイトノイズを流す
環境を整えることで、作業の切り替えコストが減り、深い集中状態(フロー状態)に入りやすくなります。これにより、同じ時間でもより多くの文章を生み出すことが可能になります。
8. バッチ処理で効率化
似た作業をまとめて行う「バッチ処理」は、記事作成の効率を大きく高める方法です。タスクの切り替えには認知的コストがかかるため、同じ種類の作業をまとめることで効率が上がります。
バッチ処理の例:
- 複数記事の構成をまとめて作成
- 複数記事の情報収集をまとめて行う
- 執筆と校正を別日に分ける
- 画像選定や装飾をまとめて行う
- 複数記事のSEO設定を一気に行う
このバッチ処理を活用すると、タスク切り替えの時間が減り、各作業に対する集中力も高まります。特に週に複数の記事を作成する場合は、各工程をバッチ処理することで大きな時間短縮になります。
9. 必要最小限の校正
記事作成で多くの時間を浪費しがちなのが校正作業です。完璧を求めすぎると、いつまでも記事が完成しない原因になります。効率化のためには、校正回数を限定することが重要です。
効率的な校正のコツ:
- 校正は最大3回までと決める
- 1回目:内容の一貫性と論理の流れ
- 2回目:文法、誤字脱字、専門用語のチェック
- 3回目:読者目線での読みやすさ確認
- チェックリストを作って効率的に確認
校正にはWebライティングチェッカーなどのツールも活用しましょう。また、完璧な記事より「公開された記事」の方が価値があると考え、過度な推敲は避けることも大切です。
10. 画像・装飾の効率化
記事の見た目を整えるための画像選定や装飾も、事前に決めたルールに従って効率的に行うことが重要です。これにより、記事ごとにデザインを考える時間を削減できます。
効率化のポイント:
- 無料素材サイトをブックマークしておく(Pixabay、Unsplashなど)
- 記事の種類ごとに装飾ルールを決めておく
- よく使う装飾(太字、マーカー、箇条書きなど)のショートカットを覚える
- アイキャッチ画像の選定基準を明確にする
- Canvaなどのテンプレートを活用する
特にWordPressのブロックエディタを使っている場合は、「再利用ブロック」機能を活用すると、よく使うデザインパターンを保存して再利用できるため、大幅な時間短縮になります。
11. タイピングスピードを上げる
基本的なスキルですが、タイピングスピードの向上は記事作成の時短に直結します。特に長文を書くことが多い場合、タイピング速度が10%上がるだけでも大きな時間節約になります。
タイピング速度向上のためのリソース:
- 寿司打、e-typing などのタイピング練習サイト
- ショートカットキーを積極的に使う
- よく使うフレーズをテキスト展開ツールに登録
- ブラインドタッチの習得
また、タイピング以外にも入力効率化の工夫として、テキスト拡張ツール(TextExpander、Cliptextなど)を使い、よく使うフレーズやあいさつ文を短いショートカットで呼び出せるようにしておくのも効果的です。
12. 記事作成の全体プロセスを最適化
最後に、記事作成全体のワークフローを見直し、最適化することで大幅な時短が可能になります。一つひとつの作業がスムーズに次の作業につながるよう、全体の流れを設計しましょう。
効率的なワークフロー例:
- 企画・キーワード選定(30分)
- 競合調査・情報収集(30分)
- 記事構成作成(20分)
- 下書き執筆(60分)
- 校正・編集(30分)
- 画像選定・装飾(20分)
- SEO設定・メタデータ入力(10分)
- 最終チェック・公開(10分)
このように各工程に明確な時間配分を設けることで、ダラダラと作業が長引くことを防ぎ、集中して効率的に記事を完成させることができます。また、工程ごとに区切ることで、途中で中断した場合も再開しやすくなります。
記事タイプ別の時短テンプレート
記事の種類によって最適な構成は異なります。ここでは、よく作成される記事タイプ別のテンプレートを紹介します。これらを活用すれば、記事の骨格をすぐに作れるため、大幅な時短につながります。
How-to記事のテンプレート
「〜の方法」「〜のやり方」といったHow-to記事は、最も需要の高い記事タイプの一つです。以下のテンプレートを活用しましょう。
| How-to記事テンプレート |
| ■H1:【実践】〜の方法・やり方を徹底解説|初心者でも失敗しない手順 |
| ■リード文 ・読者の悩みに共感 ・この記事で解決できることを提示 ・筆者の経験や実績で信頼性を示す |
| ■H2:〜とは?基本知識 ・〜の定義 ・〜の重要性や必要性 ・一般的な誤解や注意点 |
| ■H2:〜の準備に必要なもの ・必要な道具やツールのリスト ・代替品の紹介 ・準備段階での注意点 |
| ■H2:〜の手順(ステップバイステップ) ・H3:ステップ1:〜 ・H3:ステップ2:〜 ・H3:ステップ3:〜 ※各ステップで画像や図解を入れると効果的 |
| ■H2:よくある失敗とその対処法 ・トラブルシューティング ・初心者がやりがちな間違い |
| ■H2:〜の応用テクニック(上級者向け) ・基本をマスターした後のステップアップ ・効率化のコツ |
| ■H2:まとめ・次のステップ ・記事内容の要約 ・実践を促す言葉 ・関連記事や次に読むべき記事の案内 |
比較記事のテンプレート
「AとBどっちがいい?」「おすすめの〜比較」といった比較記事は、読者の意思決定を助ける記事タイプです。
| 比較記事テンプレート |
| ■H1:【徹底比較】AとBはどっちがおすすめ?|選び方のポイントと違い |
| ■リード文 ・選択に迷う読者の心情に共感 ・公平な比較をすることを約束 ・この記事で分かることを説明 |
| ■H2:AとBの基本情報 ・それぞれの特徴や定義 ・市場でのポジション ・対象ユーザー |
| ■H2:比較の視点と評価基準 ・価格 ・機能 ・使いやすさ ・サポート ・口コミ評価など |
| ■H2:AとBを徹底比較 ・H3:価格の比較 ・H3:機能の比較 ・H3:使いやすさの比較 ・H3:サポートの比較 ・H3:口コミ評価の比較 |
| ■H2:こんな人にはAがおすすめ ・Aが向いているユーザー像 ・Aの強みが活きるシーン |
| ■H2:こんな人にはBがおすすめ ・Bが向いているユーザー像 ・Bの強みが活きるシーン |
| ■H2:AとBの選び方|決定のポイント ・最終判断のための質問リスト ・優先すべき基準 |
| ■H2:まとめ:AとBどちらを選ぶべきか ・比較のおさらい ・最終的なアドバイス |
リスト記事のテンプレート
「〜のおすすめ10選」「〜するための7つの方法」といったリスト形式の記事は、情報が整理されているため読者に好まれる記事タイプです。
| リスト記事テンプレート |
| ■H1:【2024年最新】〜おすすめ10選|選び方のポイントも解説 |
| ■リード文 ・読者の悩みや探している理由に共感 ・記事の選定基準を明確に ・この記事で得られるメリット |
| ■H2:〜の選び方|失敗しないためのポイント ・選定基準1:〜 ・選定基準2:〜 ・選定基準3:〜 |
| ■H2:おすすめ〜10選 ・H3:商品/方法1:〜 ・特徴 ・メリット ・デメリット ・おすすめポイント (以下、商品/方法10まで同様に展開) |
| ■H2:【比較表】おすすめ〜10選の特徴まとめ ・価格、特徴、対象者などを比較する表 |
| ■H2:〜に関するよくある質問 ・Q&A形式で疑問に答える |
| ■H2:まとめ:あなたに最適な〜の選び方 ・記事のおさらい ・最終的なアドバイス |
これらのテンプレートを自社のブランドやターゲット読者に合わせてカスタマイズし、記事作成の定型フォーマットとして活用しましょう。テンプレートがあれば、構成を考える時間が大幅に削減できます。
AIツールを活用した最新の記事作成ワークフロー
現代の記事作成では、AIツールを効果的に活用することで、大幅な時短が可能になります。ここでは、Perplexity.AIとBing AIを活用した最新のワークフローを紹介します。
Perplexity.AIを活用した情報収集と構成作成
Perplexity.AIは、複数の情報ソースから信頼性の高い情報を収集し、整理してくれるAIツールです。記事作成の最初の段階で活用することで、情報収集と構成作成を効率化できます。
Perplexity.AIの活用手順:
- 「〜について最新の情報を教えて」と質問する
- 「〜に関する記事の構成案を作成して」と依頼する
- 「〜について専門家の意見や統計データを教えて」と具体的な情報を求める
- 「〜について記事を書く際の注意点は?」と質問する
Perplexity.AIの強みは、最新情報へのアクセスと複数ソースからの情報統合です。記事の裏付けとなる情報や専門家の見解を短時間で集められるため、記事の信頼性を高めつつ情報収集時間を大幅に短縮できます。
Bing AIで記事の下書きを自動生成
Microsoft BingのAI機能(Copilot)は、記事の下書き生成に特化した機能を持つAIツールです。構成が決まった後の文章化作業を効率化できます。
Bing AIの活用手順:
- 「作成」モードを選択する
- 「執筆分野」に記事のタイトルと見出しを入力する
- トーン(フレンドリー、プロフェッショナルなど)を選択
- 形式(記事、ブログなど)と長さを指定
- 生成された下書きをプレビュー
- 「チャット」モードに切り替えて修正指示を出す
Bing AIは文章の一貫性に優れ、指定した見出し構造に沿った記事を生成できます。生成された下書きをベースに自分の知見や経験を加えることで、オリジナリティのある記事に仕上げることができます。
AI出力の編集とブラッシュアップのコツ
AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、適切に編集してブラッシュアップすることで、質の高い記事に仕上げることが重要です。
編集のポイント:
- 事実確認を必ず行う(AIは間違った情報を提供することもある)
- 自社の経験や独自データを加える
- 実例や具体的なケーススタディを追加する
- 読者を意識した言葉遣いに調整する
- AI独特の表現や冗長な文章を修正する
- 内部リンクや外部リンクを適切に追加する
AIのアウトプットは「下書き」として捉え、それに価値を加えることで、AIだけでは作れない独自性のある記事を効率的に作成できます。
時短しながらも質の高い記事を書くポイント
時短を意識するあまり、記事の質が落ちてしまっては本末転倒です。ここでは、効率性と質の両立を図るためのポイントを紹介します。
読者視点を忘れない
いくら効率的に記事を作成しても、読者にとって価値のない記事では意味がありません。常に「この記事が読者の課題解決にどう役立つか」を考えながら執筆しましょう。
読者視点を維持するためのチェックポイント:
- 記事は読者の悩みや疑問に答えているか
- 専門用語は適切に説明されているか
- 具体例や事例が含まれているか
- 読者が次にとるべきアクションが明確か
- 記事を読んだ後、読者の状況が改善するか
読者の問題解決を最優先に考えることで、時短しながらも価値のある記事を作成できます。
オリジナリティを保つ方法
テンプレートやAIを活用しながらも、記事のオリジナリティを保つことは重要です。競合と差別化するためにも、独自の視点や経験を盛り込みましょう。
オリジナリティを高める要素:
- 独自の体験や事例
- 自社だけが持つデータや調査結果
- 業界の内部者ならではの視点や気づき
- オリジナルの図解や画像
- ユニークな切り口や問題提起
AIツールや効率化テクニックはあくまで「道具」であり、コンテンツの本質的な価値は執筆者の知見や経験から生まれます。時短テクニックを活用することで浮いた時間を、独自視点の追加や深い考察に使うことでバランスの取れた記事制作が可能になります。
SEO対策と読者体験のバランス
効率的な記事作成を目指す際も、SEOと読者体験のバランスを取ることが重要です。検索エンジンからの評価と読者満足度の両方を高める工夫をしましょう。
バランスを取るためのポイント:
- キーワードの自然な配置(詰め込みすぎない)
- 論理的で分かりやすい見出し構造
- 適度な文章の長さと段落分け
- 読者の疑問に先回りして答える
- 適切な内部リンクと外部リンク
- 視覚的要素(画像・図解)と文章のバランス
GoogleのE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を意識し、読者にとって本当に価値のあるコンテンツを効率的に提供することを心がけましょう。
プロに依頼するという選択肢
自社で記事作成を効率化する努力をしても、リソースや時間に限界がある場合もあります。そんなとき、専門家に記事作成を依頼するという選択肢も検討する価値があります。
プロに依頼するメリット:
- SEOの専門知識を持ったプロが執筆
- 社内リソースを本業に集中できる
- 一定品質の記事を安定して供給
- 最新のSEOトレンドに対応した記事制作
- 効果測定とデータに基づく改善提案
記事作成のアウトソーシングを検討する際は、合同会社Writers-hubのようなSEOコンテンツ制作の専門家に相談することをおすすめします。
Writers-hubは、SEOライティングのプロフェッショナル集団として、効果的なコンテンツマーケティングを支援しています。累計1000記事以上の制作実績を持ち、独自開発のSEO支援ツールを活用した質の高い記事構成と、コンバージョン重視のライティングが強みです。
提供サービスには以下があります:
- SEO記事コンテンツ作成:キーワード選定から記事執筆・校正、CMSへの入稿まで一貫対応
- SEOキーワード戦略設計:サイト全体のキーワード戦略と内部リンク設計を提案
- SEO記事内製化支援:社内でSEO記事を制作できる体制構築をサポート
自社でのリソースに限界を感じたら、Writers-hubのような専門家に相談することで、効率的かつ効果的なコンテンツマーケティングを実現できます。自社でのノウハウ蓄積を目指す場合でも、内製化支援を受けることで最短距離でスキルアップが可能です。
記事制作の時短と質の向上を同時に実現したい方は、ぜひWriters-hubのSEO記事コンテンツ作成やSEO記事内製化支援をご検討ください。
まとめ:記事作成の時短で生産性を高めよう
本記事では、記事作成の効率を大幅に向上させる12の方法と、効率と質を両立させるためのテクニックを紹介しました。最後にポイントをおさらいしておきましょう。
- 記事作成の効率化にはテンプレートの活用が鍵
- キーワード設計と箇条書きからの構成作りで執筆の迷いを減らす
- 音声入力やAIツールの活用で文章作成を高速化
- バッチ処理や作業環境の整備で集中力を維持
- 校正・画像選定も効率化し、完璧主義から脱却する
- 記事タイプ別のテンプレートで構成作りを簡略化
- AI活用では情報収集と下書き作成を効率化しつつ、独自価値を付加 >
- 効率化と同時に読者視点とオリジナリティを維持することが重要
- リソースに限界を感じたら専門家への依頼も検討
記事作成の時短は、単に作業を早く終わらせることが目的ではありません。効率化によって浮いた時間を、より戦略的な考察や独自コンテンツの充実、読者との関係構築など、本質的な価値創造に使うことが真の目的です。
自社での記事作成効率化に挑戦しつつも、リソースや専門知識に限界を感じたら、合同会社Writers-hubのような専門家に相談してみましょう。高品質なSEOコンテンツ制作から内製化支援まで、貴社のコンテンツマーケティングを次のレベルに引き上げるお手伝いをいたします。
記事作成の効率化で悩まれている方は、ぜひお問い合わせください。貴社のビジネスに合わせた最適なコンテンツ戦略をご提案いたします。


