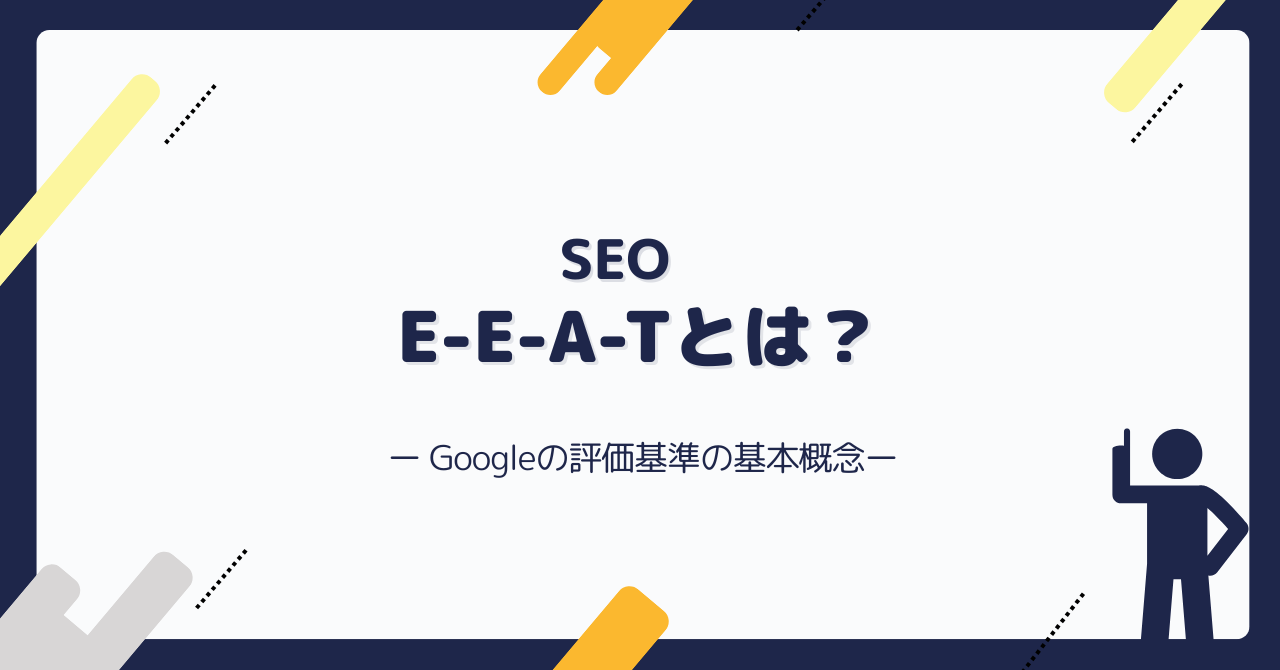
E-E-A-Tとは?Googleの評価基準の基本概念
Googleの検索アルゴリズムはますます高度化し、「質の高いコンテンツ」の定義も年々変化しています。そんな中、Google自身が検索品質評価ガイドラインで明示している「E-E-A-T」という概念が、SEO対策において非常に重要な指標となっています。
E-E-A-Tとは「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取った略語です。かつては「E-A-T」と呼ばれていましたが、2022年12月に「Experience(経験)」が追加され、現在の「E-E-A-T」となりました。
本記事では、E-E-A-Tの各要素の詳細や、SEOとの関係性、そして効果的な対策方法まで徹底解説します。Webサイトの評価を高め、検索上位を目指すための重要な知識となりますので、ぜひ最後までご覧ください。
『SEO最強』AIライティングツールで記事を量産したい人は他にいませんか?
3000記事以上の執筆・編集経験を持つSEO専門ライターが、2年間の試行錯誤の末に開発した革新的AIシステム。
- キーワードを入力するだけで5万字超のプロンプトが生成
- ClaudeやChatGPTにコピペするだけで装飾済みの原稿が一発完成
- ライター外注費を最大90%削減可能
-------------------
![]() こんな課題を抱えていませんか?
こんな課題を抱えていませんか?
- 「コンテンツ制作費、もっと安くならないの?」と言われ失注が増えてきた
- ライターとのコミュニケーションコストや管理が大変
- いくらAIツールを試しても本当に「自分が書かなくていいレベル」にならない
-------------------
「一気通貫Pro」があれば解決します!
「立ち上げ4ヶ月で4万PV達成!(上場企業)」
「外注費を90%削減できた。一気通貫Proの原稿が良すぎて6割は時間削減できている(Web制作会社)」
「低コストのSEO記事制作プランを自信を持って提案できるようになり受注率が向上(制作会社)」
他のAIツールとの決定的な違いはこの3点!
- システム会社やSEO会社ではなく現役ライターが開発したから、プロが書いたような「使える」原稿が出力される
- プロンプトを出力するツールなので、生成AIに「ここをもっとこうして」と追加指示で修正も簡単(他のAIツールは修正は人力)
- 生成AIのプランに準じて事実上無制限に記事作成可能(他の多くは月間制限あり)
-------------------
![]() 30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
AIの出力そのままの無料デモ記事の作成も承っています。まずは実際の出力をご確認ください!
E-E-A-Tとは?Googleの評価基準の基本概念
E-E-A-Tとは、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった略語で、Googleの検索品質評価ガイドラインで定義されているWebサイトの評価基準です。「イーイーエーティー」または「ダブルイーエーティー」と読みます。
この概念は元々「E-A-T」(「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」)として2014年に導入されましたが、2022年12月のガイドライン更新で「Experience(経験)」が追加され、現在の「E-E-A-T」となりました。
E-E-A-Tは、Googleが品質評価者(人間のレーター)に対して示している評価基準であり、アルゴリズムに直接組み込まれているわけではありません。しかし、品質評価者の判断結果はアルゴリズムの改善に使用されるため、E-E-A-Tの各要素を意識したWebサイト運営がSEOにとって非常に重要となります。
SEOの基本概念については「【2025年最新】SEOとは?初心者でもわかる基本と効果的な対策法」で詳しく解説しています。
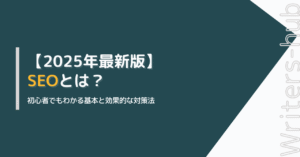
E-A-TからE-E-A-Tへ:何が変わったのか
2022年12月、Googleは検索品質評価ガイドラインを更新し、従来の「E-A-T」に「E(Experience:経験)」を追加しました。これにより、コンテンツ作成者自身の実体験に基づく情報が、より高く評価されるようになりました。
この変更は、単なる知識や専門性だけでなく、実際の経験から得られた洞察や体験談を重視する流れを示しています。例えば、特定の製品レビューを書く場合、その製品を実際に使用した経験があるかどうかが重要視されるようになったのです。
最新のSEOトレンドについては「【2025年最新】SEOトレンド完全ガイド これからの検索順位を決める7つの重要変化」もご覧ください。
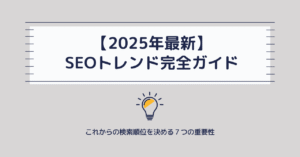
Googleが品質評価ガイドラインでE-E-A-Tを重視する理由
Googleが検索品質評価ガイドラインでE-E-A-Tを重視する最大の理由は、ユーザーに価値のある、信頼性の高い情報を提供するためです。インターネット上には膨大な情報が存在し、その中には不正確な情報や誤解を招くコンテンツも少なくありません。
Googleの使命は「世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすること」です。この使命を達成するためには、検索結果の品質を担保する必要があります。E-E-A-Tは、そのための重要な評価基準となっているのです。
特に健康や金融など、人々の生活や幸福に直接的な影響を与える可能性のある「YMYL(Your Money Your Life)」カテゴリのサイトでは、E-E-A-Tの基準がより厳しく適用されます。これについては後ほど詳しく解説します。
E-E-A-Tの4つの要素を詳しく解説
E-E-A-Tは4つの要素から構成されています。それぞれの要素について詳しく見ていきましょう。
1. 経験(Experience)とは?
経験(Experience)とは、コンテンツ作成者が実際にその分野や製品・サービスを体験したことがあるかどうかを指します。実際の経験に基づいた情報は、理論的な知識だけに基づく情報よりも具体的で役立つことが多いため、Googleは実体験に基づくコンテンツを高く評価します。
例えば、以下のようなコンテンツは「経験」の要素が強いと言えるでしょう:
- 実際に使用した製品のレビュー
- 実際に訪れた場所の旅行記
- 実際に体験したサービスの感想
- 実際に試した方法やテクニックの解説
- 実際に経験した問題とその解決方法
「経験」を示すには、具体的なエピソードや体験談を交えることが効果的です。「〜を使ってみたところ、〜という結果になりました」「実際に〜してみて感じたのは〜です」といった表現を使うことで、読者に実体験に基づく情報であることを伝えることができます。
質の高いコンテンツについては「結局のところ「質の高いコンテンツ」って何だろう」で詳しく解説しています。
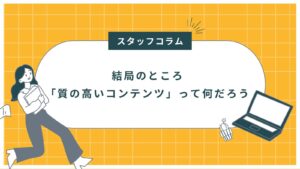
2. 専門性(Expertise)とは?
専門性(Expertise)とは、そのトピックに関する深い知識や技術を持っているかどうかを指します。専門性の高いコンテンツは、そのトピックについて包括的かつ正確な情報を提供します。
専門性は、正式な資格や学位だけでなく、長年の経験や自己学習によっても獲得できます。例えば、医療情報を提供する場合は医師や看護師などの医療専門家によるコンテンツが高く評価されますが、DIYやホビーなどの分野では、正式な資格がなくても豊富な経験と知識を持つ「日常的な専門家」のコンテンツも評価されます。
Googleが推奨する「自社のコンテンツに専門性があるかをチェックするための質問」には、以下のようなものがあります:
- コンテンツは専門知識を持つ人によって作成または編集されていますか?
- コンテンツはトピックを包括的に、明確に、完全に扱っていますか?
- コンテンツは表面的ではなく、洞察に富んだ分析や情報を提供していますか?
- 検索結果の他のページと比較して、コンテンツは実質的な価値を提供していますか?
ライターの専門性については「「良いライターがいない」の解決策を考える」も参考にしてください。
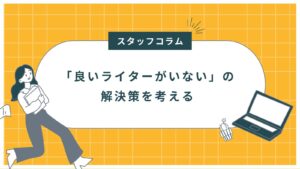
3. 権威性(Authoritativeness)とは?
権威性(Authoritativeness)とは、そのウェブサイトや著者が業界内で認められた権威であるかどうかを指します。権威性は、外部からの評価や認識によって判断されます。
権威性を示す要素には、以下のようなものがあります:
- 信頼性の高いウェブサイトからの被リンク
- 業界メディアでの引用や言及
- 専門家からの推薦
- 権威ある組織との提携
- 業界内での評判や認知度
権威性は一朝一夕に構築できるものではなく、長期的な取り組みによって徐々に確立されていくものです。しかし、一度確立された権威性は、サイト全体の評価を大きく向上させる効果があります。
4. 信頼性(Trustworthiness)とは?
信頼性(Trustworthiness)とは、ウェブサイトや情報源が信頼できるものであるかどうかを指します。信頼性は、正確さ、透明性、誠実さなどによって判断されます。
信頼性を示す要素には、以下のようなものがあります:
- 正確で最新の情報を提供していること
- 情報源や引用を明示していること
- 運営者情報が明確であること
- セキュリティ対策が施されていること(HTTPSの導入など)
- 広告とコンテンツの区別が明確であること
- プライバシーポリシーや利用規約が明示されていること
信頼性は、ユーザーがウェブサイトを安心して利用するための基盤となる要素です。特に個人情報やクレジットカード情報などを扱うサイトでは、信頼性の確保が非常に重要となります。
企業の情報発信については「企業の情報発信方法7選|目的やメリット・炎上しないための注意点も解説」もご覧ください。

E-E-A-Tの要素の重要度:どれが最も大切か
4つの要素のうち、どれが最も重要かという疑問をお持ちの方もいるでしょう。結論から言えば、これらの要素の重要度はトピックやサイトの性質によって異なります。
例えば、医療情報を扱うサイトでは「専門性」と「信頼性」が特に重要になりますが、製品レビューサイトでは「経験」が最も重視されます。また、ニュースサイトでは「権威性」と「信頼性」が特に重要です。
ただし、すべてのサイトに共通して言えるのは、「信頼性」がE-E-A-Tの基盤となる要素であるということです。いくら専門性や権威性があっても、信頼性がなければユーザーの支持は得られません。まずは信頼性を確保した上で、他の要素にも取り組むことが重要です。
YMYLとE-E-A-Tの深い関係性
E-E-A-Tを理解する上で欠かせないのが「YMYL」という概念です。YMYLとE-E-A-Tは密接に関連しており、特にYMYLカテゴリのサイトではE-E-A-Tの基準がより厳格に適用されます。
YMYLとは何か
YMYL(Your Money Your Life)とは、人々の幸福、健康、金銭、安全に影響を与える可能性のあるトピックやページのことを指します。Googleは、YMYLカテゴリのコンテンツに対して特に高い品質基準を設けています。
YMYLカテゴリには、以下のようなものが含まれます:
- 健康・医療情報
- 金融・投資情報
- 法律・法的アドバイス
- ニュース・時事問題
- オンラインショッピング
- 住宅・不動産情報
- 教育・進路に関する情報
- 安全に関する情報
YMYLサイトでE-E-A-Tが重要視される理由
YMYLカテゴリのコンテンツは、人々の重要な意思決定や健康・安全に直接影響する可能性があるため、Googleはこれらのトピックに対して特に厳格な品質基準を適用しています。不正確または誤解を招くYMYL情報は、ユーザーに深刻な影響を与える可能性があるため、Googleはこれらのトピックに関する低品質コンテンツを検索結果から排除しようと努力しています。
例えば、医療情報を提供するサイトでは、医療専門家による執筆や監修、信頼できる情報源からの引用、最新の医学的知見の反映などが求められます。同様に、金融アドバイスを提供するサイトでは、金融の専門家による執筆や透明性の高い情報提供が重要となります。
つまり、YMYLカテゴリのサイトでは、E-E-A-Tの各要素をより意識的に、より高いレベルで満たす必要があるのです。特に「専門性」と「信頼性」の要素が重視されます。
| カテゴリ | E-E-A-Tの重要度 | 特に重視される要素 |
| 医療・健康情報 | 非常に高い | 専門性、信頼性 |
| 金融・投資情報 | 非常に高い | 専門性、信頼性 |
| 法律・法的アドバイス | 非常に高い | 専門性、信頼性 |
| ニュース・時事 | 非常に高い | 権威性、信頼性 |
| 製品レビュー | 高い | 経験、信頼性 |
| レシピ・料理 | 中程度 | 経験、専門性 |
| 趣味・エンターテイメント | 低~中程度 | 経験 |
SEOにおけるE-E-A-Tの重要性
E-E-A-Tは、Googleの検索品質評価ガイドラインで定義されている概念であり、品質評価者(人間のレーター)がWebサイトの品質を評価する際の基準として使用されています。では、SEOにおいてE-E-A-Tはどのような意味を持つのでしょうか。
E-E-A-TがSEO評価に与える影響
E-E-A-Tは直接的にはアルゴリズムに組み込まれているわけではありませんが、品質評価者の評価結果はアルゴリズムの改善に使用されるため、間接的にSEO評価に大きな影響を与えています。
Googleは「コアアルゴリズムアップデート」と呼ばれる大規模な検索アルゴリズムの更新を定期的に実施していますが、これらのアップデートでは特にYMYLカテゴリのサイトに対してE-E-A-Tの要素を重視する傾向が強まっています。
2018年8月のいわゆる「健康アップデート」以降、健康や医療に関する情報を提供するサイトでは、医師や専門家による執筆・監修が明示されているサイトが上位表示されるようになりました。同様に、金融情報サイトでも、専門家による情報提供が重視されるようになっています。
E-E-A-Tを意識したサイト運営は、短期的なSEO対策ではなく、長期的なサイトの評価向上につながる取り組みです。一時的なテクニックでは対応できない、サイトの本質的な品質向上が求められています。
E-E-A-Tスコアは実在するのか
「E-E-A-Tスコア」という明確な数値がGoogleのアルゴリズム内に存在するわけではありません。E-E-A-Tは品質評価の概念であり、単一のスコアや直接的な順位決定要因ではないのです。
ただし、Googleは品質評価者の評価結果を機械学習モデルのトレーニングデータとして使用しており、これによりアルゴリズムがE-E-A-Tの概念を「学習」していると考えられます。つまり、アルゴリズムはE-E-A-Tの各要素を直接測定しているわけではなく、これらの要素を示す様々なシグナルを複合的に評価していると考えられます。
例えば、以下のような要素がE-E-A-Tのシグナルとして機能している可能性があります:
- 被リンクの質と量(権威性のシグナル)
- 著者情報の明示(専門性のシグナル)
- サイトのセキュリティ対策(信頼性のシグナル)
- 具体的な体験談の記載(経験のシグナル)
- 情報の正確性と最新性(信頼性のシグナル)
E-E-A-Tを高める効果的な10の方法
E-E-A-Tの概念と重要性を理解したところで、次はE-E-A-Tを高めるための具体的な方法を見ていきましょう。ここでは、E-E-A-Tの各要素を強化するための効果的な10の方法を紹介します。
経験(Experience)を高める方法
経験の要素を強化するには、実際の体験に基づくコンテンツを充実させることが重要です。以下の方法が効果的です:
1. 具体的な体験談や事例を盛り込む
実際の体験から得られた具体的なエピソードや事例を記事に盛り込みましょう。「〜を使ってみたところ、〜という結果になりました」「実際に〜してみて感じたのは〜です」といった表現を使うことで、読者に実体験に基づく情報であることを伝えることができます。
例えば、製品レビューを書く場合は、実際に使用した感想や使い勝手、メリット・デメリットなどを具体的に記載します。旅行記事なら、実際に訪れた際の様子や体験、おすすめポイントなどを詳細に描写します。
2. ビフォーアフター形式のコンテンツを作成する
「ビフォー」と「アフター」を明確に示すことで、実体験の説得力を高めることができます。例えば、ダイエット方法の記事なら、実施前と実施後の体重や体型の変化を具体的な数値や写真で示します。Web制作会社なら、リニューアル前とリニューアル後のサイトデザインや成果の比較を示します。
こうしたビフォーアフター形式のコンテンツは、単なる理論や知識だけでなく、実際に効果があったという証拠を示すことができるため、読者の信頼を獲得しやすくなります。
3. お客様の声や事例を掲載する
自社の製品やサービスを利用したお客様の声や事例を掲載することで、第三者の経験という形で「経験」の要素を強化できます。お客様インタビューや導入事例、レビューなどを記事化し、実際のユーザーがどのような体験をしたかを伝えましょう。
この方法は、自社の直接的な経験だけでなく、顧客の視点からの経験も示すことができるため、より多角的な「経験」の提示が可能になります。また、同じような課題を持つ見込み客にとっても参考になる情報となります。
専門性(Expertise)を高める方法
専門性の要素を強化するには、深い知識と技術を示すコンテンツを提供することが重要です。以下の方法が効果的です:
4. 著者情報や運営者情報を充実させる
記事の著者や運営者の経歴、資格、実績などを明示し、その分野における専門性を示しましょう。記事ごとに著者プロフィールを設置したり、「About Us」ページで運営者の詳細情報を提供したりすることが効果的です。
例えば、医療系サイトなら医師や専門家の資格や所属医療機関、経歴などを記載します。金融系サイトなら、ファイナンシャルプランナーや証券アナリストなどの資格保有者が執筆していることを明示します。
また、一般的なトピックでも、その分野での経験年数や実績、得意分野などを記載することで、専門性をアピールすることができます。
5. 特定のテーマに特化したサイト運営を心がける
様々なトピックを浅く扱うよりも、特定のテーマに特化し、そのテーマについて深く掘り下げたコンテンツを提供することで専門性を示すことができます。サイトのテーマを絞り込み、そのテーマに関するあらゆる側面をカバーする包括的なコンテンツを作成しましょう。
例えば、「美容全般」というテーマよりも「40代女性のアンチエイジング」に特化した方が、より深い専門性を示すことができます。同様に、「マーケティング全般」よりも「中小企業のためのインスタグラムマーケティング」のように特化すると良いでしょう。
6. 一次情報や独自データを提供する
独自の調査やリサーチ、インタビューなどによって得られた一次情報やデータを提供することで、専門性を示すことができます。他のサイトにはない独自の情報やデータは、そのトピックに対する深い理解と取り組みを示す証拠となります。
例えば、アンケート調査の実施とその結果分析、業界関係者へのインタビュー、データの収集と可視化などが効果的です。また、自社で実施した実験や検証の結果、事例研究なども有効です。
コンテンツ制作については「コンテンツ制作とは?目的や種類、効果的な作り方とポイントを徹底解説」もご覧ください。
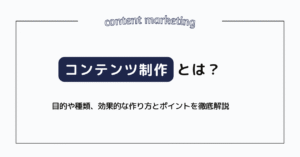
権威性(Authoritativeness)を高める方法
権威性の要素を強化するには、外部からの評価や認識を高めることが重要です。以下の方法が効果的です:
7. 質の高い被リンクを獲得する
信頼性の高いウェブサイトからのリンクを獲得することで、権威性を高めることができます。被リンクは、他のサイトからの「推薦」と見なされ、Googleはこれを権威性の重要なシグナルとして捉えています。
質の高い被リンクを獲得するためには、以下のような方法があります:
- 価値のある独自コンテンツの作成
- 業界メディアやニュースサイトへの情報提供
- 業界イベントやセミナーへの参加・登壇
- 他のブログやメディアへのゲスト投稿
- 業界団体や協会への加入・連携
8. サイテーションを獲得する
サイテーション(ブランド名や会社名の言及)を増やすことも、権威性を高める効果的な方法です。SNSや各種メディア、ディレクトリサイトなどで自社名が言及されることで、Googleはそのブランドの認知度や重要性を評価します。
サイテーションを獲得するためには、以下のような方法があります:
- Googleビジネスプロフィールの作成・最適化
- 業界ディレクトリへの登録
- プレスリリースの配信
- SNSでの積極的な情報発信
- 業界イベントやコミュニティへの参加
Webサイトの集客については「Web集客とは?13種類の方法と成功事例、効果的な戦略を徹底解説」で詳しく解説しています。
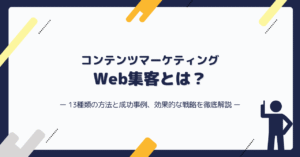
信頼性(Trustworthiness)を高める方法
信頼性の要素を強化するには、透明性の確保とセキュリティの強化が重要です。以下の方法が効果的です:
9. サイトのSSL化(HTTPS対応)を徹底する
ウェブサイトをSSL化(HTTPS対応)することで、セキュリティを強化し、信頼性を高めることができます。HTTPSは、ユーザーとサーバー間の通信を暗号化し、情報の改ざんや盗聴を防ぐ技術です。
Googleは2014年からHTTPSをランキング要因の一つとして導入しており、セキュアなサイトを優先的に表示する姿勢を明確にしています。現在ではHTTPSは標準となっており、HTTPのままでは「保護されていない通信」という警告がブラウザに表示されることもあります。
SSL証明書は無料のものから有料のものまで様々ありますが、個人ブログや小規模サイトであれば無料のLet’s Encryptなどで十分対応可能です。
10. 信頼できる情報源を引用・参照する
権威ある情報源や公的機関からの情報を引用・参照することで、コンテンツの信頼性を高めることができます。特に事実に基づく主張や統計データを提示する際は、信頼できる出典を明示することが重要です。
例えば、医療情報を提供する際は医学論文や厚生労働省のデータを、金融情報を提供する際は金融庁や日本銀行のデータを引用するなど、権威ある情報源からの情報を活用しましょう。
また、引用・参照する際は以下の点に注意すると良いでしょう:
- 情報源のURL、著者名、公開日などを明記する
- 最新の情報を参照する(古い情報は更新する)
- 引用と自分の意見・解釈を明確に区別する
- 複数の情報源を参照し、バランスの取れた情報を提供する
オウンドメディアの運用については「オウンドメディア運用ガイド|成功のポイントと効果的な運営方法を徹底解説」も参考にしてください。
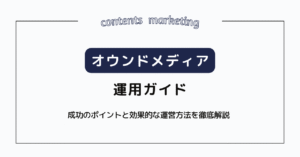
E-E-A-T対策の成功事例
E-E-A-T対策を効果的に実施し、検索順位の向上に成功した事例を見ていきましょう。これらの事例から、E-E-A-T対策の具体的な効果とアプローチ方法を学ぶことができます。
医療情報サイトの事例
ある健康情報サイトは、2018年の「健康アップデート」後に検索順位が大幅に下落しました。原因を分析した結果、医療専門家による監修や執筆が明示されていないことが問題と判断し、以下の対策を実施しました:
- 各記事に医師や専門家の監修者情報を追加
- 監修者の経歴、資格、専門分野を詳細に記載
- 医学論文や公的機関のデータを引用し、出典を明記
- 古い情報を更新し、最新の医学的知見を反映
- 医師や専門家による「よくある質問」コーナーの設置
これらの対策を実施した結果、約3か月後から検索順位が徐々に回復し、半年後には多くのキーワードで以前よりも高い順位を獲得することに成功しました。特に「専門性」と「信頼性」の要素を強化したことが効果的だったと考えられます。
金融ブログの事例
個人投資家が運営する金融ブログは、初めは検索上位に表示されていましたが、コアアルゴリズムアップデート後に順位が下落しました。YMYLカテゴリであるにもかかわらず、運営者の専門性や信頼性が明確に示されていなかったことが原因でした。以下の対策を実施しました:
- 運営者のプロフィールページを作成し、金融分野での経験や資格を詳細に記載
- 記事内に実際の投資経験や結果を具体的に記載
- 情報源として金融庁や日本銀行などの公的機関データを活用し、出典を明記
- 専門家へのインタビュー記事を定期的に掲載
- 金融に特化したコンテンツのみを提供し、他のトピックは別サイトに移行
これらの対策により、「経験」と「専門性」の要素が強化され、約6か月後には主要キーワードでの検索順位が回復。特に「実際の投資経験」を詳細に記載した記事が高評価を得ました。
レビューサイトの事例
製品レビューを提供するサイトは、2021年の「製品レビューアップデート」後に大幅な順位下落を経験しました。原因は、実際に製品を使用した経験が示されておらず、一般的な情報の羅列に留まっていたことでした。以下の対策を実施しました:
- 実際に製品を購入・使用した証拠として、オリジナル写真や動画を追加
- 使用期間や使用環境などの具体的な情報を追加
- 長所と短所を具体的に記載し、使用して初めて分かる詳細情報を提供
- 複数の製品を比較検証した独自のデータを提供
- レビュアーのプロフィールを詳細に記載し、その分野での経験や知識を示す
これらの対策により、「経験」の要素が大幅に強化され、アップデート後に失った検索順位を約4か月で回復。特に具体的な使用感や比較データを提供した記事が好調でした。
上位表示するための方法は「Googleで検索上位を獲得する方法15選!SEO対策の仕組みからコツまで徹底解説」で詳しく解説しています。
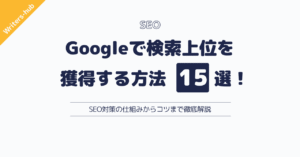
E-E-A-T対策でよくある間違いとその回避法
E-E-A-T対策を行う際によくある間違いと、その回避方法について解説します。これらの落とし穴を避けることで、より効果的なE-E-A-T対策を実施することができます。
虚偽の専門性や経験をアピールする
実際には持っていない資格や経験を偽って記載することは、発覚した場合に信頼性を大きく損なう行為です。Googleの品質評価者は、専門性や経験の主張が事実かどうかをオンラインで調査することもあります。
回避法:実際の経験や専門性に基づいたコンテンツ作成に注力しましょう。専門性が不足している分野については、専門家への取材や監修依頼、共同執筆などの方法で補うことが効果的です。自分の知識や経験の範囲内で誠実に情報を提供することが、長期的な信頼構築につながります。
形式的な対策に終始する
「著者情報を追加すれば良い」「SSLを導入すれば良い」など、形式的な対策だけでE-E-A-Tが向上すると考えるのは誤りです。E-E-A-Tは総合的な品質評価の概念であり、表面的な対応だけでは効果は限定的です。
回避法:本質的な品質向上を目指しましょう。形式的な対策も重要ですが、それだけでなく、コンテンツ自体の質を高め、ユーザーにとって真に価値のある情報を提供することが大切です。例えば、著者情報を追加するだけでなく、その著者が本当に価値ある情報を提供しているかどうかが重要です。
過剰な自己宣伝に走る
権威性をアピールするあまり、実績や資格を過剰に強調しすぎると、かえって信頼性を損なう可能性があります。特に内容を伴わない自己宣伝は、ユーザーに「怪しい」という印象を与えかねません。
回避法:バランスの取れた情報提供を心がけましょう。自己の専門性や権威性は控えめに、しかし明確に示し、メインはあくまでもユーザーに価値を提供するコンテンツであるべきです。第三者からの評価や証言を活用すると、より説得力が増します。
トピックの枠を超えて拡大しすぎる
サイトの専門性を高めるためには、特定のテーマに特化することが効果的ですが、アクセス数を増やすために関連性の薄いトピックまで手を広げるケースがあります。これは専門性の希薄化につながり、サイト全体の評価を下げる可能性があります。
回避法:サイトのテーマと強い関連性のあるコンテンツに集中しましょう。もし異なるテーマのコンテンツを提供したい場合は、別サイトとして運営することを検討してください。サイトの専門性と一貫性を保つことが、E-E-A-Tの評価向上につながります。
古いコンテンツを放置する
一度公開したコンテンツを更新せずに放置すると、情報が古くなり信頼性が低下します。特に医療や金融など、最新情報が重要な分野では致命的な問題となり得ます。
回避法:定期的なコンテンツの見直しと更新を行いましょう。特に重要な記事や古くなりやすい情報を含む記事は、定期的な更新スケジュールを設けることをおすすめします。更新日を明示し、常に最新の情報を提供する姿勢を示すことで、信頼性の向上につながります。
まとめ:E-E-A-Tを活用したSEO戦略の構築
本記事では、Googleの評価基準であるE-E-A-Tについて詳しく解説してきました。E-E-A-Tの4つの要素「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」は、現代のSEO対策において非常に重要な概念です。
E-E-A-Tは直接的なランキング要因ではありませんが、Googleのアルゴリズムに間接的に影響を与え、特にYMYLカテゴリのサイトでは決定的な要素となります。E-E-A-Tを意識したサイト運営は、短期的なSEO対策ではなく、サイトの本質的な品質向上につながる長期的な取り組みです。
E-E-A-Tを高めるためには、以下のポイントを押さえることが重要です:
- 経験(Experience):実体験に基づくコンテンツを提供し、具体的なエピソードや事例を盛り込む
- 専門性(Expertise):著者情報を充実させ、特定のテーマに特化したコンテンツを深く掘り下げる
- 権威性(Authoritativeness):質の高い被リンクやサイテーションを獲得し、業界内での評価を高める
- 信頼性(Trustworthiness):サイトのセキュリティを強化し、信頼できる情報源を引用・参照する
これらの要素をバランスよく強化することで、Googleからの評価だけでなく、ユーザーからの信頼も獲得できるでしょう。最終的には、「検索エンジンのために最適化する」というよりも、「ユーザーに真の価値を提供する」という姿勢が、SEOの成功につながります。
E-E-A-T対策は一朝一夕に成果が出るものではありませんが、着実に取り組むことで、長期的かつ持続可能なSEO効果を得ることができます。ぜひ本記事で紹介した方法を参考に、自社サイトのE-E-A-T向上に取り組んでみてください。
E-E-A-T対策のプロフェッショナルに相談する
E-E-A-T対策は、SEOの中でも特に専門知識と経験が求められる分野です。自社でE-E-A-T対策を進めるのが難しい場合や、より効果的な対策を実施したい場合は、プロフェッショナルに相談することをおすすめします。
合同会社Writers-hubは、SEOコンテンツ制作のプロフェッショナル集団として、E-E-A-Tを考慮した高品質なコンテンツ制作をサポートしています。1000記事以上の制作実績と独自のSEO支援ツールを活用し、検索上位を狙いながらコンバージョンにも繋がるコンテンツを提供しています。
Writers-hubでは以下のようなサービスを提供しています:
- SEO記事コンテンツ作成:キーワード選定から記事執筆・校正、CMSへの入稿まで一貫してサポート
- SEOキーワード戦略設計:ビジネス内容やターゲットを踏まえた効果的なキーワード戦略を立案
- SEO記事内製化支援:社内でSEO記事を執筆できる体制づくりをサポート
特に「E-E-A-T」の観点では、以下のような強みがあります:
- 経験(Experience):実際の使用感や体験に基づいた具体的な記述で、読者の共感と信頼を獲得
- 専門性(Expertise):各分野の知識を持つライターが執筆し、専門的かつ正確な情報を提供
- 権威性(Authoritativeness):業界トレンドや競合分析を踏まえた、説得力のあるコンテンツ作成
- 信頼性(Trustworthiness):信頼できる情報源の引用と、透明性の高い情報提供を徹底
E-E-A-T対策に悩んでいる方、検索順位の向上を目指している方は、ぜひWriters-hubにご相談ください。お客様のビジネス目標に合わせた最適なSEO戦略と高品質なコンテンツ制作をサポートします。


