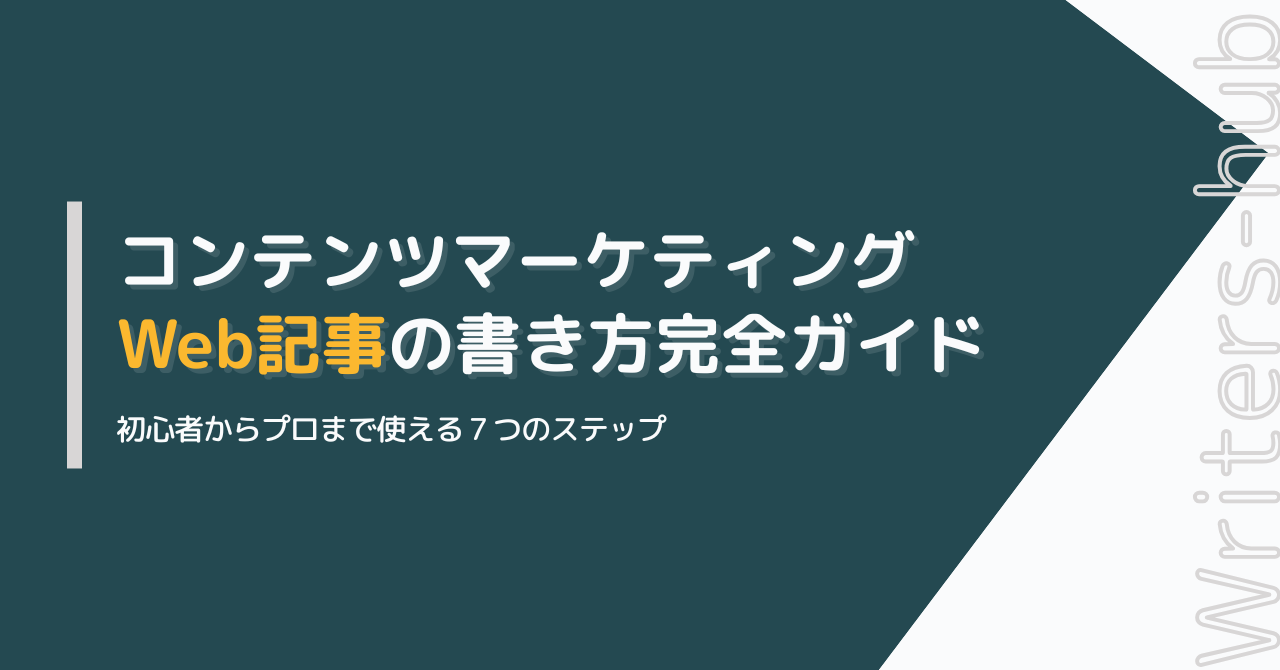
Web記事の書き方完全ガイド|初心者からプロまで使える7つのステップとコツ
Webライターとして活躍したい、自社のブログやメディアを立ち上げたい、あるいはすでに運営しているけれど成果が出ないとお悩みではありませんか?実は、Web記事の書き方には「読まれる記事」と「読まれない記事」を分ける明確な法則があります。
Web記事の書き方を学ぶことで、読者の悩みを解決し、検索上位を獲得できるコンテンツを作れるようになります。初心者でも取り組みやすい記事作成のステップや、プロが実践しているライティングのコツを知ることで、効果的な情報発信が可能になるのです。
本記事では、Web記事制作の前準備から執筆、推敲までの全プロセスを7つのステップで徹底解説します。さらに読まれる記事を書くためのコツや、よくあるミスとその対策法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
『SEO最強』AIライティングツールで記事を量産したい人は他にいませんか?
3000記事以上の執筆・編集経験を持つSEO専門ライターが、2年間の試行錯誤の末に開発した革新的AIシステム。
- キーワードを入力するだけで5万字超のプロンプトが生成
- ClaudeやChatGPTにコピペするだけで装飾済みの原稿が一発完成
- ライター外注費を最大90%削減可能
-------------------
![]() こんな課題を抱えていませんか?
こんな課題を抱えていませんか?
- 「コンテンツ制作費、もっと安くならないの?」と言われ失注が増えてきた
- ライターとのコミュニケーションコストや管理が大変
- いくらAIツールを試しても本当に「自分が書かなくていいレベル」にならない
-------------------
「一気通貫Pro」があれば解決します!
「立ち上げ4ヶ月で4万PV達成!(上場企業)」
「外注費を90%削減できた。一気通貫Proの原稿が良すぎて6割は時間削減できている(Web制作会社)」
「低コストのSEO記事制作プランを自信を持って提案できるようになり受注率が向上(制作会社)」
他のAIツールとの決定的な違いはこの3点!
- システム会社やSEO会社ではなく現役ライターが開発したから、プロが書いたような「使える」原稿が出力される
- プロンプトを出力するツールなので、生成AIに「ここをもっとこうして」と追加指示で修正も簡単(他のAIツールは修正は人力)
- 生成AIのプランに準じて事実上無制限に記事作成可能(他の多くは月間制限あり)
-------------------
![]() 30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
AIの出力そのままの無料デモ記事の作成も承っています。まずは実際の出力をご確認ください!
Web記事とは|その特徴と基本的な考え方
はじめに、Web記事の基本的な特徴と考え方について理解しておきましょう。Web記事とは、インターネット上で公開されるテキストコンテンツのことで、ブログ記事やメディア記事、コラムなどさまざまな形態があります。
Web記事と紙媒体の違い
Web記事と紙媒体(雑誌や新聞など)では、読まれ方に大きな違いがあります。この違いを理解することが、効果的なWeb記事を作成する第一歩です。
| 項目 | Web記事 | 紙媒体 |
| 読み方 | スキャンする(流し読み) | じっくり読む |
| 情報取得 | 必要な情報だけ拾い読み | 前から順に読む傾向 |
| 滞在時間 | 平均30秒~2分程度 | 数分~数十分 |
| 競合 | 無数の類似記事がワンクリックで閲覧可能 | 手元にある限られた媒体 |
| 検索性 | 検索エンジンで見つけられる必要がある | 購入や配布により読者に届く |
Web記事の最大の特徴は「スキャン(流し読み)される前提で書く」という点です。読者はじっくり読むのではなく、欲しい情報を素早く見つけることを優先します。そのため、見出しの工夫や段落を短くするなど、視認性を高める工夫が必要です。
Web記事に求められる3つの要素
効果的なWeb記事には、以下の3つの要素が欠かせません。
- 有用性:読者の悩みや疑問を解決する実用的な情報
- 検索適性:検索エンジンで上位表示されるSEO対策
- 読みやすさ:視認性が高く、理解しやすい文章構造
これら3つの要素をバランスよく取り入れることで、多くの読者に価値を提供できる記事が完成します。特に初心者の方は、「自分の書きたいこと」よりも「読者が知りたいこと」を優先して考えることが大切です。
Web記事の書き方7ステップ|完成までの流れを解説
ここからは、クオリティの高いWeb記事を作成するための7ステップを詳しく解説します。この流れに沿って記事を作成することで、効率的に読者の役に立つコンテンツを生み出せるようになります。
STEP1:記事の目的とターゲットを明確にする
記事作成の第一歩は、「なぜこの記事を書くのか」「誰に読んでもらいたいのか」を明確にすることです。目的とターゲットが曖昧なまま執筆を始めると、内容がぶれてしまい、読者に価値を届けられません。
記事の目的には主に以下のようなものがあります:
- 読者の悩みや疑問を解決する
- 商品やサービスの認知を広げる
- 専門知識を分かりやすく伝える
- コンバージョン(問い合わせや購入など)を獲得する
また、ターゲットを具体的に想定することで、読者が求める情報や表現方法を選びやすくなります。年齢、性別、職業、悩みなど、できるだけ詳細にペルソナ(想定読者像)を設定しましょう。
例:「Web記事の書き方について知りたい20代後半の女性。マーケティング会社で働いており、社内ブログを担当することになったが、効果的な記事の書き方がわからず悩んでいる。」
STEP2:キーワードリサーチと検索意図の把握
読者に記事を届けるためには、彼らが使う検索キーワードを把握し、そのキーワードで上位表示を狙う必要があります。効果的なキーワードリサーチによって、記事のテーマや方向性が明確になり、読者のニーズに応える内容を作れます。
キーワードを選定する際は、以下の点を考慮しましょう:
- 検索ボリューム(月間検索数)
- 競合の多さ(難易度)
- 検索意図(情報収集、比較検討、購入意向など)
- ビジネス目標との関連性
キーワードが決まったら、そのキーワードで検索するユーザーがどんな情報を求めているのか(検索意図)を理解することが重要です。例えば、「Web記事 書き方」というキーワードでは、初心者向けの基本的な執筆方法からプロ向けのテクニックまで、さまざまな情報ニーズが考えられます。
Google検索の上位10件程度をチェックし、どのような内容がユーザーに支持されているのかを分析しましょう。特に注目すべき点は:
- 記事の形式(ハウツー、リスト形式、Q&Aなど)
- 取り上げられているトピック
- 記事の構成や見出し
- 情報の詳細度
STEP3:競合記事の分析と記事構成の作成
STEP2で調査した内容をもとに、競合記事をさらに詳しく分析し、独自の価値を持つ記事構成を作成します。記事構成は記事の設計図であり、この段階で内容を練り上げておくことで、執筆の効率と質が大幅に向上します。
効果的な記事構成を作成するポイントは以下の通りです:
- 上位記事の共通点を抽出する:検索上位の記事で共通して取り上げられているトピックは、読者が求める情報の核心部分である可能性が高いため、必ず含めましょう。
- 独自の視点や情報を加える:競合記事にはない独自のアングル、事例、データなどを盛り込むことで差別化を図ります。
- 論理的な流れを整える:読者が自然に理解できるよう、情報を論理的に配置します。一般的に「概要→詳細→応用」の流れが分かりやすいでしょう。
- 見出しで内容が伝わるようにする:H2、H3などの見出しだけを読んでも記事の全体像が把握できるよう、具体的でわかりやすい見出しをつけます。
記事構成はWordやExcelなどのツールで作成し、各見出しごとに盛り込むべき内容の要点をメモしておくと良いでしょう。また、この段階で必要な参考資料やデータも洗い出しておくと、執筆がスムーズに進みます。
STEP4:魅力的なタイトルとリード文を書く
記事の構成ができたら、読者の興味を引くタイトルとリード文(導入部)を考えます。タイトルは記事の「顔」であり、クリック率を大きく左右する重要な要素です。リード文は記事冒頭の数行で、読者が「続きを読むべきかどうか」を判断する材料となります。
効果的なタイトルのポイント:
- ターゲットキーワードを含める:SEO的にも重要ですが、読者が求める内容であることが一目でわかります。
- 具体的な数字を入れる:「7つのステップ」「5つのコツ」など具体性があると信頼感が増します。
- 読者のメリットを示す:「〜できるようになる」「〜が解決する」など、記事を読むことで得られる価値を明示します。
- 30文字程度に収める:検索結果で途切れずに表示されるよう、30文字前後を目安にします。
リード文作成のポイント:
- 読者の悩みや問題点に共感する:「〜でお悩みではありませんか?」など、読者の課題を言語化します。
- 記事で得られる解決策を示唆する:「本記事では〜について解説します」と、内容を簡潔に予告します。
- 3段落程度でコンパクトにまとめる:長すぎると読者が本文に到達する前に離脱してしまうため注意しましょう。
例:記事タイトル「Web記事の書き方完全ガイド|初心者からプロまで使える7つのステップとコツ」
STEP5:読者の悩みを解決する本文を執筆する
ここからいよいよ本文の執筆に入ります。準備段階でしっかりと記事構成を練っていれば、あとは各見出しに沿って内容を肉付けしていくだけです。読者の視点に立ち、悩みを解決する情報を分かりやすく提供することを心がけましょう。
効果的な本文執筆のポイント:
- PREP法を活用する:「Point(結論)→Reason(理由)→Example(例)→Point(結論)」の順で説明することで、論理的でわかりやすい文章になります。
- 一文一義を心がける:一つの文には一つの内容だけを書き、複数の内容を詰め込まないようにします。
- 専門用語は解説する:読者のレベルに合わせて専門用語の説明を適宜入れます。
- 段落を短くする:3〜4行程度の短い段落で区切ると読みやすくなります。
- 具体例や事例を交える:抽象的な説明だけでなく、具体例を挙げることで理解しやすくなります。
- 図解や表を活用する:複雑な情報は図解や表にまとめると視覚的に理解しやすくなります。
執筆中に行き詰まったら、一度離れて気分転換をするか、別の見出しから書き進めるのも効果的です。無理に一気に書き上げようとせず、適度に休憩を取りながら進めましょう。
STEP6:読みやすさを向上させる推敲と編集
本文が完成したら、読みやすさを向上させるための推敲と編集を行います。記事の質を高めるのは執筆後の修正作業であり、この段階を軽視すると記事の効果が半減してしまいます。
推敲のチェックポイント:
- 文章の流れ:全体を通して論理的につながっているか
- 重複表現:同じ内容を繰り返し説明していないか
- 文末表現:「です」「ます」など同じ文末が3回以上続いていないか
- 漢字とひらがなの比率:漢字が多すぎると読みにくく、少なすぎると幼稚な印象になるため、バランスが取れているか
- 一文の長さ:長すぎる文がないか(40~60文字程度が目安)
- 指示語の使用:「これ」「それ」などの指示語が何を指しているか明確か
- 誤字脱字:特に固有名詞や数字の間違いがないか
また、この段階で視覚的な読みやすさも向上させましょう:
- 重要なポイントを太字にする
- 箇条書きや番号リストを活用する
- 適切な見出しレベル(H2、H3など)を使用する
- 図解や画像を効果的に配置する
- 引用や注釈を適切に表示する
推敲は自分で行うだけでなく、できれば第三者に読んでもらい、わかりにくい点や改善点をフィードバックしてもらうと良いでしょう。
STEP7:効果測定とリライトで記事の質を高める
記事を公開したら終わりではありません。公開後の効果測定とリライト(修正・追記)を行うことで、継続的に記事の質を高めていくことが重要です。特にSEOを意識する場合、検索エンジンの評価は時間とともに変化するため、定期的な見直しが必要になります。
効果測定のポイント:
- アクセス数:記事への訪問者数の推移
- 滞在時間:ユーザーが記事に留まる時間
- 直帰率:他のページを見ずに離脱する割合
- 検索順位:狙ったキーワードでの検索順位
- コンバージョン率:記事経由の問い合わせや購入などの成果
これらの指標を分析し、改善すべき点が見つかったらリライトを行います。特に以下のような場合は積極的に記事を更新しましょう:
- 競合記事と比較して情報が不足している
- 古い情報や事実誤認がある
- 読者からの質問が多く寄せられる(=説明が不十分)
- 検索順位が下落している
- 新たな情報や事例が追加できる
定期的なリライトにより、記事の鮮度と品質が維持され、長期的に価値を提供し続けることができます。
読まれるWeb記事を書くための5つのコツ
ここからは、Web記事の書き方の基本ステップに加えて、より読まれる記事にするための実践的なコツを5つご紹介します。これらのテクニックを意識することで、読者の共感を得やすく、読み進めてもらいやすい記事が書けるようになります。
1. ユーザーの検索意図を理解する
検索意図(ユーザーが特定のキーワードで検索する際に求めている情報)を正確に把握することは、読まれる記事を書く上で最も重要なポイントです。同じキーワードでも、ユーザーによって求める情報は異なります。
検索意図は主に以下の4つに分類できます:
- 情報検索型:知識や情報を得たい(例:「Web記事 書き方」)
- ナビゲーション型:特定のサイトや場所を探している(例:「Writers-hub コンタクト」)
- トランザクション型:購入や申し込みなどのアクションを起こしたい(例:「Webライター 料金 相場」)
- コマーシャル型:商品やサービスを比較検討している(例:「SEOツール 比較」)
検索意図を理解するには、そのキーワードで実際に検索し、上位表示されているページの傾向を分析するのが効果的です。上位記事が解説記事なのか、サービス紹介なのか、比較記事なのかを確認し、読者が求める情報タイプに合わせた記事を作成しましょう。
2. スキャンしやすい文章構造を意識する
先述の通り、Web上の文章は「流し読み(スキャン)」される傾向にあります。読者が求める情報を素早く見つけられるよう、スキャンしやすい文章構造を意識することが重要です。
スキャンしやすい文章にするコツ:
- 結論から先に書く:「起承転結」ではなく「結起承転」の順で情報を提示します。
- 見出しを充実させる:見出しだけを読んでも内容が理解できるよう、具体的かつ情報量のある見出しをつけます。
- 段落の先頭に重要情報を置く:各段落の最初の文に要点を凝縮します。
- 箇条書きや番号リストを活用する:情報を整理して視認性を高めます。
- 強調表示を効果的に使う:太字やマーカーなどで重要ポイントを目立たせます。
- 適切な空白を設ける:段落間や要素間に余白を設け、視覚的な呼吸を確保します。
これらの工夫により、読者は自分に必要な情報を効率よく見つけることができ、記事の満足度が高まります。
3. 読者の信頼を得る根拠のある情報提供
インターネット上には膨大な情報があふれており、読者は信頼できる情報源を求めています。記事の信頼性を高めるためには、主張や説明に根拠を示すことが重要です。
信頼性を高める情報の示し方:
- 信頼できる情報源からの引用:公的機関や権威あるメディア、専門家の見解などを引用します。
- 具体的なデータや統計の活用:「多くの人が」ではなく「78%の人が」など、具体的な数字で示します。
- 実例や事例の紹介:実際の成功事例や失敗事例を交えることで説得力が増します。
- 自身の経験に基づく情報:執筆者自身の経験談は読者にとって貴重な一次情報となります。
- 専門家や監修者の設置:可能であれば、専門家による監修や確認を受けることで信頼性が高まります。
情報源を明示することは、読者への誠実さの表れでもあります。「〜と言われています」「〜のようです」といった曖昧な表現は避け、具体的な出典や根拠を示すよう心がけましょう。
4. 独自性と付加価値のある内容を盛り込む
検索上位を獲得し、読者の心に残る記事にするためには、他の記事にはない独自の視点や価値を提供することが重要です。単なる情報の寄せ集めではなく、あなた(あるいはあなたの組織)だからこそ提供できる価値を盛り込みましょう。
独自性を高める方法:
- オリジナルの調査や分析結果:独自のアンケートやデータ分析は大きな差別化要因になります。
- 実践に基づく独自のノウハウ:実務経験から得た具体的なテクニックや裏技を紹介します。
- 業界特有の視点や事例:特定の業界や分野に特化した情報は専門性を示せます。
- オリジナルの図解やイラスト:視覚的に情報を整理したオリジナルコンテンツは価値が高いです。
- 既存情報の新しい切り口:既知の情報でも、新しい視点や組み合わせで提示すれば価値が生まれます。
どんなトピックでも、あなたなりの視点や経験、解釈を加えることで独自性のある記事になります。「誰かが書いた内容をまとめただけ」にならないよう、自分の言葉で語ることを心がけましょう。
5. 適切な内部リンクと外部リンクの設置
Web記事の効果を最大化するためには、適切なリンクの設置も重要です。内部リンク(自サイト内の他ページへのリンク)と外部リンク(他サイトへのリンク)を戦略的に配置することで、SEO効果の向上やユーザー体験の改善につながります。
効果的なリンク設置のポイント:
- 関連性の高いページへリンクする:読者が次に知りたいと思う情報ページへのリンクを提供します。
- 自然な文脈でリンクを設置する:「こちら」などの一般的な言葉ではなく、内容を表す具体的なアンカーテキストを使います。
- 情報の補足として外部リンクを活用する:信頼性の高いサイトへのリンクは、あなたの記事の信頼性も高めます。
- 適切な量を心がける:リンクが多すぎると読者の集中力が分散するため、本当に必要なものだけにします。
- CTAを効果的に配置する:コンバージョンにつながるリンク(問い合わせや資料請求など)は記事の流れを考慮して配置します。
内部リンクは「読者を自サイト内に留める」「サイト全体のSEO評価を高める」という二つの重要な役割を果たします。読者の行動導線を考慮し、次に見てほしいページへ自然に誘導できるようリンクを設計しましょう。
Web記事でやりがちな7つのミスと対策法
ここからは、Web記事作成でよく見られるミスとその対策法について解説します。これらの落とし穴を理解し、あらかじめ避けることで、より効果的な記事が書けるようになります。
冗長な表現や無駄な言い回し
初心者ライターがよく陥るのが、同じ内容を冗長に繰り返したり、無駄な言い回しを使ったりすることです。Web記事では簡潔さが重要であり、余計な表現は読者の負担になります。
NG例:
「このようなWeb記事の書き方のポイントとしては、まず最初に考えるべきことは、記事の目的をしっかりと明確に定めておくということが非常に重要であるといえます。」
改善例:
「Web記事を書く際は、まず記事の目的を明確にしましょう。」
対策:
- 推敲時に「この文は必要か?」と各文をチェックする
- 「〜のようなもの」「〜といえるでしょう」などの曖昧表現を削除する
- 「非常に」「とても」などの強調語を必要最低限にする
一文が長すぎる文章
一文に多くの情報を詰め込みすぎると、読者が理解しにくくなります。Web記事では一文40〜60文字程度を目安にし、複数の内容は別の文に分けるのが効果的です。
NG例:
「Web記事を書く際には構成を考えることが大切ですが、その前にターゲットと目的を明確にしておく必要があり、さらにキーワードリサーチも行ってから、競合記事の分析も行って、それらを踏まえた上で魅力的な見出しと内容を考えなければなりません。」
改善例:
「Web記事を書く際には構成を考えることが大切です。ただし、その前にターゲットと目的を明確にしておく必要があります。さらにキーワードリサーチや競合記事の分析も行いましょう。これらを踏まえた上で、魅力的な見出しと内容を考えていきます。」
対策:
- 接続詞(そして、しかし、また)を使って文を分割する
- 一文一義を意識し、複数の内容は別の文に分ける
- 読み上げたときに息継ぎが必要になる文は分割する
指示語の多用による分かりにくさ
「これ」「それ」「あれ」などの指示語を多用すると、何を指しているのか分かりにくくなります。特に段落が変わると、指示語の対象が不明確になりやすいため注意が必要です。
NG例:
「Web記事を書く際はSEO対策も重要です。これを怠ると、検索結果に表示されにくくなります。それによって読者数が減少する可能性があります。こうなると、せっかく書いた記事が無駄になってしまいます。」
改善例:
「Web記事を書く際はSEO対策も重要です。SEO対策を怠ると、検索結果に表示されにくくなります。検索順位の低下によって読者数が減少する可能性があります。読者数の減少により、せっかく書いた記事が無駄になってしまいます。」
対策:
- 指示語を使わず、具体的な名詞を繰り返し使う
- 指示語を使う場合は、何を指しているか明確にする
- 長い文章や段落をまたぐ場合は特に注意する
同じ文末表現の連続
「です」「ます」「しょう」など、同じ文末表現が連続すると単調な印象を与え、読者の興味を失わせてしまいます。文末表現にバリエーションを持たせることで、読みやすさと印象が向上します。
NG例:
「Web記事を書く際は構成が重要です。見出しを工夫することも大切です。読者が求める情報を提供することがポイントです。」
改善例:
「Web記事を書く際は構成が重要です。また、見出しを工夫することも読者の理解を助けます。何よりも、読者が求める情報を提供することがポイントといえるでしょう。」
対策:
- 「です・ます」「でしょう・ましょう」「だ・である」などを適度に混ぜる
- 体言止め(名詞で文を終える)を効果的に使う
- 文の構造自体を変えてリズム感を出す
根拠のない情報提供
「〜と言われています」「〜のようです」など、根拠が示されていない情報は読者の信頼を損ないます。情報の出典を明らかにし、可能な限り具体的なデータや事例を示すことが大切です。
NG例:
「最近のWeb記事は2,000文字以上が良いと言われています。また、見出しは多いほど効果的だという意見もあります。」
改善例:
「Googleの調査によると、検索上位のWeb記事は平均2,000文字以上の文章量があります(Google公式ブログ、2023年)。また、SEOツールXYZの分析では、見出しが5つ以上ある記事はCTRが25%向上することが報告されています。」
対策:
- 情報の出典(調査結果、統計、専門家の見解など)を明記する
- 根拠が示せない情報は記事に含めない
- 自分の意見や経験である場合は、その旨を明示する
モバイル環境を考慮していない構成
現在、Webトラフィックの半数以上はモバイル端末からのアクセスです。スマートフォンでの閲覧を考慮した記事構成や表示を意識しないと、多くの読者を失う可能性があります。
モバイル閲覧時の問題点:
- 長すぎる段落は画面を何度もスクロールする必要がある
- 横に広すぎる表は表示が崩れる
- 文字が小さすぎると読みにくい
- 画像が大きすぎると読み込みに時間がかかる
対策:
- 段落を短く(3〜4行程度)保つ
- 複雑な表は横スクロールになることを想定し、シンプルにする
- 見出しと本文の区別がはっきりするようデザインする
- 画像は最適化して読み込み速度を確保する
- 実際にスマートフォンで表示確認をする
SEO対策の過剰な意識
SEO対策は重要ですが、キーワードの詰め込みや不自然な文章構成など、過剰なSEO対策は読者体験を損ない、逆効果になることがあります。Googleの検索アルゴリズムは進化し、読者にとって有用なコンテンツを評価する方向に変化しています。
NG例:
「Web記事の書き方について解説します。Web記事の書き方は初心者にとって重要です。Web記事の書き方を学べば、効果的なWeb記事の書き方がマスターできます。」
改善例:
「この記事では、効果的なWeb記事の書き方について初心者にも分かりやすく解説します。基本的なポイントからプロのテクニックまで、段階的に学べる内容になっています。」
対策:
- まずは読者にとって有用な内容を第一に考える
- キーワードは自然な文脈で使用する
- 過度な繰り返しを避け、類義語や関連語を適切に使う
- 見出しや画像ALTテキストなど、適切な場所でキーワードを使用する
Web記事の種類別|効果的な書き方のポイント
Web記事には様々な種類があり、それぞれ最適な書き方が異なります。ここでは代表的な記事タイプ別に、効果的な書き方のポイントを解説します。目的に合わせた記事タイプを選び、そのフォーマットに沿って書くことで、読者の期待に応える記事が作成できます。
ハウツー記事の効果的な書き方
ハウツー記事は「どうやって〇〇するか」という疑問に答える記事タイプです。料理レシピや操作手順、問題解決方法など、具体的な方法を解説します。明確なステップと詳細な説明が求められるため、実践しやすさが重要なポイントになります。
ハウツー記事の書き方のポイント:
- 明確な手順をステップバイステップで説明する:番号付きリストなどを使い、順序を明確にします。
- 各ステップに具体的な説明を加える:「なぜそうするのか」の理由も含めると理解しやすくなります。
- 視覚的な補助を提供する:可能であれば、各ステップの画像や動画を追加します。
- 想定される問題と解決策を示す:「うまくいかない場合は〜」といった補足情報も役立ちます。
- 成功の例や結果を示す:最終的にどうなるかのイメージを提供します。
- 必要な道具や前提知識を明記する:読者が準備できるよう、必要なものを最初に示します。
ハウツー記事は実用性が高く、問題解決を求める読者に直接的な価値を提供できます。その分、実際に試してみて確実に効果がある方法を紹介することが信頼性につながります。
問題解決型記事の効果的な書き方
問題解決型記事は、読者が抱える特定の悩みや課題に対して解決策を提示する記事です。ハウツー記事と似ていますが、より問題の分析と複数の解決策の提示に重点が置かれます。読者の痛点を深く理解し、実現可能な解決策を示すことが成功の鍵です。
問題解決型記事の書き方のポイント:
- 問題の明確な定義から始める:読者が「自分の悩みだ」と共感できる問題提起をします。
- 問題が起こる原因や背景を説明する:なぜその問題が発生するのかの理解を深めます。
- 複数の解決策を提示する:状況や好みに応じて選べるよう、複数のアプローチを示します。
- 各解決策のメリット・デメリットを示す:読者が自分に合った方法を選べるよう情報を提供します。
- 実践のためのステップを示す:具体的にどう行動すれば良いかを明確にします。
- 成功事例や証言を含める:その解決策で実際に問題が解決した例を示します。
問題解決型記事は読者の悩みに寄り添い、実践的な価値を提供することで強い信頼関係を構築できます。「あなたは一人じゃない」というメッセージを伝えると、共感を得やすくなります。
比較・レビュー記事の効果的な書き方
比較・レビュー記事は、製品やサービス、方法などを比較検討し、評価する記事タイプです。購入や選択の意思決定をサポートする情報を提供します。公平で客観的な評価と、読者の選択に役立つ情報の提示が重要です。
比較・レビュー記事の書き方のポイント:
- 明確な比較基準を設定する:機能、価格、使いやすさなど、評価の軸を明確にします。
- 客観的なデータと主観的な感想を区別する:事実とあなたの意見を明確に分けて記述します。
- 表や図を使って比較情報を視覚化する:一覧で比較できると読者の理解が進みます。
- メリットとデメリットを公平に示す:良い点だけでなく、改善点も誠実に伝えます。
- どんな人に向いているかを明示する:「〜な人におすすめ」といった情報が選択の参考になります。
- 結論や推奨を明確に示す:読者が求めるのは最終的な判断材料です。
比較・レビュー記事では、バイアスのない公正な評価が信頼性の鍵となります。利害関係がある場合は明示し、できるだけ実際の使用経験に基づいた情報を提供するよう心がけましょう。
ニュース記事の効果的な書き方
ニュース記事は、新しい出来事や最新情報を伝えるための記事タイプです。時事性が高く、事実を正確に伝えることが求められます。5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を押さえた簡潔明瞭な文章が基本です。
ニュース記事の書き方のポイント:
- 逆ピラミッド構造を採用する:最も重要な情報を冒頭に置き、徐々に詳細や背景情報を展開します。
- 事実と意見を明確に分ける:客観的事実を中心に伝え、解説や意見は別途示します。
- 信頼できる情報源を明示する:情報の出典を明らかにし、裏付けを取ります。
- 中立的な表現を心がける:バイアスのない言葉遣いで事実を伝えます。
- 関連する背景情報を提供する:出来事の文脈を理解するための情報を補足します。
- 見出しは事実に基づく明確なものにする:誤解を招くようなセンセーショナルな見出しは避けます。
ニュース記事では、事実確認の徹底と情報の鮮度が重要です。誤った情報を広めることのないよう、複数の情報源で確認する習慣をつけましょう。また、新しい情報が入った場合は、適宜記事を更新することも大切です。
プロのWeb記事制作を依頼するメリットと注意点
Web記事の書き方を学んでも、時間や人的リソースの制約から自社での記事作成が難しい場合もあります。ここでは、自社で記事を書くメリット・デメリットと、プロに依頼するメリットについて解説します。
自社でWeb記事を書くメリットとデメリット
まずは、社内リソースでWeb記事を作成する場合のメリットとデメリットを理解しましょう。状況に応じた最適な選択ができるよう、両面から検討することが大切です。
自社で記事を書くメリット:
- 自社の専門知識を直接活かせる:社内の専門家の知見をダイレクトに反映できます。
- コストを抑えられる可能性がある:外注費用が発生しません。
- 情報の正確性を確保しやすい:専門的な内容も社内で確認できます。
- 自社の独自性を表現しやすい:企業文化や価値観を自然に反映できます。
- 社内のライティングスキルが向上する:継続的な執筆で社員のスキルアップにつながります。
自社で記事を書くデメリット:
- 本業の時間が削られる:記事作成に相当の時間がかかります。
- Web記事のノウハウが不足する可能性:SEOやコンテンツマーケティングの専門知識が必要です。
- 客観的な視点が不足しがち:自社視点に偏った内容になる可能性があります。
- 品質の安定が難しい:担当者のスキルや状況により品質にばらつきが出ます。
- 継続的な更新が難しくなる:業務が忙しくなると後回しにされがちです。
プロに依頼するメリットとコスト感
Web記事の制作をプロに依頼する場合のメリットと、一般的なコスト感について解説します。投資対効果を考慮し、自社のニーズに合った外注先を選ぶことが重要です。
プロに依頼するメリット:
- 品質と専門性の高い記事が得られる:SEOやライティングのプロフェッショナルが対応します。
- 社内リソースを本業に集中できる:記事作成の負担から解放されます。
- 継続的な更新が可能:定期的な記事提供を依頼できます。
- 客観的な視点が入る:第三者視点での内容構成や表現が可能です。
- 最新のSEOトレンドに対応:常に最新の知見を取り入れた記事作成が期待できます。
- 効果測定とフィードバックの仕組み:記事の効果を分析し改善提案を受けられます。
一般的なコスト感:
| サービス区分 | 価格帯(目安) | 特徴 |
| クラウドソーシング | 5,000円〜2万円/記事 | 比較的安価だが品質にばらつきがある。簡単な記事向き。 |
| フリーランスライター | 1万円〜5万円/記事 | 個人の専門性により品質が変わる。継続的な関係構築が可能。 |
| Web制作会社 | 2万円〜10万円/記事 | 安定した品質だが比較的高額。デザインや実装も含めた総合的な提案が得られる。 |
| コンテンツマーケティング会社 | 3万円〜20万円/記事 | 戦略立案から効果測定まで一貫したサポート。高度な専門性と品質が期待できる。 |
これらの価格帯は一般的な目安であり、記事の文字数、専門性、納期などによって変動します。重要なのは単純な価格比較ではなく、自社の目的と予算に合ったサービスを選択することです。
依頼先の選び方と確認すべきポイント
Web記事制作を外部に依頼する際は、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。長期的な関係構築を視野に入れ、以下のポイントを確認しましょう。
依頼先選びで確認すべきポイント:
- 実績とポートフォリオ:過去の制作実績やサンプル記事を確認し、品質や方向性が自社に合っているか判断します。
- 専門分野とSEOの知見:自社の業界知識があるか、SEO対策の実績や知識があるかを確認します。
- プロセスと納期の管理:記事作成のプロセスが明確で、納期の厳守が期待できるか確認します。
- コミュニケーション体制:担当者との連絡がスムーズか、要望の反映や修正依頼がしやすい体制か確認します。
- 料金体系の透明性:料金の内訳や追加料金の発生条件が明確か確認します。
- 修正対応の柔軟性:納品後の修正対応がどの程度含まれているか確認します。
- 著作権や二次利用の条件:制作物の権利関係や利用条件を事前に確認します。
- 守秘義務の遵守:機密情報の取り扱いについての姿勢を確認します。
依頼前に小規模な案件から始めるなど、試験的な取り組みも効果的です。また、複数の候補から比較検討することで、より自社に合ったパートナーを見つけることができるでしょう。
Writers-hubに相談するメリット
Web記事制作のプロフェッショナル集団であるWriters-hubは、SEOに強いコンテンツ作成を得意としています。検索流入を狙った記事作成から内製化支援まで、幅広いサービスを提供していますので、Web記事作成でお悩みの方はぜひご相談ください。
Writers-hubに依頼するメリット:
- 1000記事以上の実績によるノウハウ:累計1000本超の記事制作経験を活かし、様々なジャンルで成果の出るコンテンツを提供します。
- 独自ツールで網羅的な構成作成:独自開発のSEO支援ツールを使用し、検索ユーザーの意図を網羅した質の高い記事構成を作成します。
- コンバージョン重視のライティング:検索上位を狙うだけでなく、記事内で読者の課題を洗い出し「自社サービスで解決できる」と自然に訴求して成果(CV)につなげます。
- 公開後の効果測定と改善提案:記事公開後も定期的に検索順位や流入をチェックし、必要に応じてリライト案を提示して改善します。
- SEOキーワード戦略設計サービス:クライアントのビジネス内容やターゲットを踏まえ、SEO集客に有効なキーワード群とコンテンツ戦略をサイト単位で設計します。
- SEO記事内製化支援:自社に蓄積された専門知識やノウハウを活用し、外部ライターに頼らず社員がSEO記事を執筆できる体制づくりをサポートします。
Writers-hubの特徴は、単なる記事制作だけでなく、戦略立案から効果測定、さらには内製化支援まで一貫したサービスを提供している点です。「記事を作って終わり」ではなく、継続的なコンテンツマーケティングの伴走者として、クライアントのビジネス成長を支援します。
また、AIの活用や最新のSEOトレンドへの対応など、常に最先端の知見を取り入れた提案が可能です。Web記事による集客やブランディングにお悩みの方は、ぜひWriters-hubにご相談ください。
まとめ:効果的なWeb記事作成で読者とつながる
本記事では、Web記事の書き方について7つのステップを中心に詳しく解説しました。効果的なWeb記事作成のポイントをおさらいしましょう。
- Web記事は「スキャン(流し読み)される」という特性を理解し、読みやすさを重視する
- 記事作成前の準備(目的設定、ターゲット分析、キーワードリサーチ)が成功の鍵
- 読者の検索意図を理解し、求められる情報を網羅する記事構成を作成する
- タイトルとリード文に特に注力し、読者の興味を引く工夫をする
- 本文は「結論→理由→具体例→結論」の流れで、分かりやすく論理的に書く
- 推敲と編集の段階で読みやすさを向上させる工夫を加える
- 公開後も効果測定とリライトを継続し、記事の価値を維持・向上させる
Web記事作成は一朝一夕で習得できるものではありませんが、基本的な考え方と手順を理解し、継続的に実践することで必ず上達します。読者にとって真に価値ある情報を、分かりやすく提供することを常に心がけましょう。
自社での記事作成に限界を感じたり、より専門的な支援が必要だと感じたりした場合は、Web記事制作のプロであるWriters-hubにお気軽にご相談ください。キーワード選定から記事執筆・公開後の効果測定まで、一貫したサポートで御社のコンテンツマーケティングを成功に導きます。
効果的なWeb記事で読者とつながり、ビジネスの成長を加速させましょう。


