
コンテンツマーケティングの基礎知識を総まとめ|やり方から成果につなげる方法まで徹底解説
コンテンツマーケティングは、インターネットを活用した集客手法として近年大きな注目を集めています。有益な情報を発信しながら顧客との関係を深め、最終的に売り上げや問い合わせにつなげることを狙う取り組みです。ただし一口に「コンテンツマーケティング」といっても、どのように始めればよいか悩む方は少なくありません。
そこで本記事では、コンテンツマーケティングの基礎知識をあらためて整理し、具体的なやり方や成果につなげるためのポイントを詳しく解説します。実践ステップや注意点も取り上げていますので、ぜひ最後までご覧ください。
『SEO最強』AIライティングツールで記事を量産したい人は他にいませんか?
3000記事以上の執筆・編集経験を持つSEO専門ライターが、2年間の試行錯誤の末に開発した革新的AIシステム。
- キーワードを入力するだけで5万字超のプロンプトが生成
- ClaudeやChatGPTにコピペするだけで装飾済みの原稿が一発完成
- ライター外注費を最大90%削減可能
-------------------
![]() こんな課題を抱えていませんか?
こんな課題を抱えていませんか?
- 「コンテンツ制作費、もっと安くならないの?」と言われ失注が増えてきた
- ライターとのコミュニケーションコストや管理が大変
- いくらAIツールを試しても本当に「自分が書かなくていいレベル」にならない
-------------------
「一気通貫Pro」があれば解決します!
「立ち上げ4ヶ月で4万PV達成!(上場企業)」
「外注費を90%削減できた。一気通貫Proの原稿が良すぎて6割は時間削減できている(Web制作会社)」
「低コストのSEO記事制作プランを自信を持って提案できるようになり受注率が向上(制作会社)」
他のAIツールとの決定的な違いはこの3点!
- システム会社やSEO会社ではなく現役ライターが開発したから、プロが書いたような「使える」原稿が出力される
- プロンプトを出力するツールなので、生成AIに「ここをもっとこうして」と追加指示で修正も簡単(他のAIツールは修正は人力)
- 生成AIのプランに準じて事実上無制限に記事作成可能(他の多くは月間制限あり)
-------------------
![]() 30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
AIの出力そのままの無料デモ記事の作成も承っています。まずは実際の出力をご確認ください!
コンテンツマーケティングとは
まずはコンテンツマーケティングの定義から確認します。コンテンツマーケティングとは、有益なコンテンツ(情報)を定期的に提供しながら、見込み顧客や既存顧客との関係を築くマーケティング手法です。
この「コンテンツ」とは、記事・動画・メールマガジン・SNS・ホワイトペーパーなどさまざまな形式が含まれます。自社の製品やサービスを直接売り込むのではなく、まずは悩みや疑問を解決する情報を提供し、ファンになってもらう点が特徴です。
従来の広告のようにプッシュ型で顧客にアプローチする「プッシュ型マーケティング」とは異なり、コンテンツをきっかけとして自然な流入を狙う「プル型マーケティング」であることが大きな違いです。
詳しい解説は「コンテンツマーケティングとは?定義からメリット・手法・成功事例まで徹底解説」をご覧ください。

コンテンツマーケティングが注目される背景
なぜコンテンツマーケティングが注目されるのでしょうか。主な理由を挙げます。
消費者の購買行動が変化している
インターネットの普及に伴い、消費者が自らの意思で情報を収集する機会は大きく増えました。テレビCMや紙媒体での広告だけではなく、検索エンジンやSNSを用いて情報を集めてから購入や契約を検討する人が多くなっています。
こうした変化に合わせて、押し付け型の広告ではなく、有益な情報を発信して自発的なアクションを促す手法が求められるようになりました。そのため、多くの企業がコンテンツマーケティングに注力しているのです。
重要性については「コンテンツマーケティングの重要性とは?目的やメリット、成功へのステップを徹底解説」で詳しく解説しています。

Googleの検索エンジン評価が「質重視」に移行
検索エンジンのアルゴリズムは絶えずアップデートされており、質の高いコンテンツを提供するWebサイトが上位表示されやすい傾向にあります。以前はキーワードを無理に詰め込み大量のページを用意すれば検索上位を狙えた時代もありましたが、今ではその手法は通用しません。
読者にとって有益な情報を届け続けるサイトこそが、検索エンジンから高い評価を受けるようになったのです。結果として、独自の見解や専門性の高い情報を定期的に発信するコンテンツマーケティングが重要視される流れとなっています。
SEOについては「【2025年最新】SEOとは?初心者でもわかる基本と効果的な対策法」も参考にしてください。
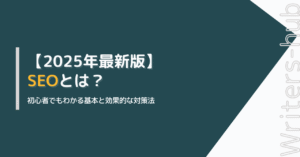
広告費の高騰とターゲットの細分化
インターネット広告に取り組む企業が増えたことで、クリック単価が上昇している分野もあります。特に競合が多い商材では、大きな広告費用を投下しても期待するリターンを得られない可能性があります。
さらにターゲットのニーズが多様化し、細分化が進んでいることもあり、広告だけに依存するのではなく、見込み顧客との長期的な関係構築を図るためのコンテンツマーケティングに価値が見いだされています。
メリットについては「コンテンツマーケティングのメリットを徹底解説|成果を高める手法や注意点も紹介」で詳しく解説しています。
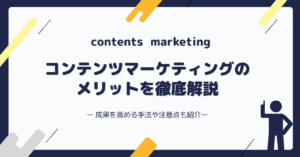
コンテンツマーケティングの基本要素を押さえる
コンテンツマーケティングを正しく運用するには、いくつかの基本要素を理解する必要があります。ここでは代表的な概念を取り上げます。
戦略の立て方は「コンテンツマーケティング戦略の立て方を徹底解説|成果を伸ばす具体的なステップ」をご覧ください。

トリプルメディア
コンテンツマーケティングでは、発信するメディアを使い分けることが重要です。「トリプルメディア」とは以下の3種類のメディアを指します。
- オウンドメディア(Owned Media)
企業が保有するメディア(自社Webサイト、ブログ、SNSアカウントなど)。自社でコントロールしやすく、戦略的に情報を発信できる点が利点。 - ペイドメディア(Paid Media)
広告など、有料枠を使って発信するメディア。広告枠を買うため即効性は高いが、費用はかかる。 - アーンドメディア(Earned Media)
口コミやSNSでの拡散など、第三者から「獲得」するメディア。信頼度が高いが、企業が直接コントロールしにくい。
コンテンツマーケティングを始めるにあたっては主にオウンドメディアの運用から取り組みますが、ペイドメディアやアーンドメディアとの組み合わせも意識するとより効果を高められます。
企業の情報発信については「企業の情報発信方法7選|目的やメリット・炎上しないための注意点も解説」で詳しく解説しています。

ペルソナの設計
ペルソナとは「自社商品・サービスを利用する典型的な顧客像」を詳細に描いたもので、コンテンツマーケティングでは欠かせない考え方です。具体的には、性別、年齢、職業、年収、趣味、生活パターン、課題感などを設定します。
ペルソナを明確にすることで、コンテンツの方向性がぶれず、訴求力が向上します。たとえば「小規模事業者の経理担当者をターゲットとする」なら、具体的にどのような悩みや疑問を抱えているか把握できるため、ニーズを満たす情報を提供しやすくなるでしょう。
企画立案については「成功するコンテンツマーケティングの企画立案の作り方|企画書を作る際のポイントも」も参考にしてください。
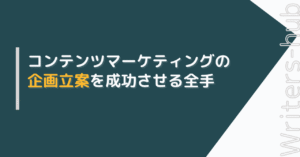
カスタマージャーニーマップ
カスタマージャーニーマップは、ターゲットが認知から購入・ファン化に至るまでの行動や心理を時系列でまとめたものです。ペルソナ視点で「どこで情報を知り、どのように比較検討し、何をきっかけに購入(問い合わせ)に至るか」を可視化します。
このマップをもとにユーザーが最適なタイミングで最適なコンテンツに触れられるように設計していくと、コンテンツマーケティングの効果は高まりやすくなります。
フレームワークについては「コンテンツマーケティングに役立つフレームワーク活用ガイド|戦略設計から差別化まで網羅」で詳しく解説しています。

代表的なコンテンツの種類と事例
コンテンツマーケティングで活用される形式は多岐にわたります。ここでは代表例を挙げ、それぞれの特徴を簡単に説明します。
様々な手法は「コンテンツマーケティング手法を包括解説|実施メリットや成功事例も紹介」もご覧ください。
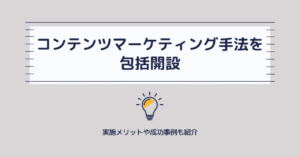
ブログ・オウンドメディア
自社サイト内で専門性やノウハウを記事化する形式です。たとえば「コンテンツマーケティングのやり方」や「Web集客を高めるコツ」といったテーマを記事にして配信することで、検索経由やSNSから読者を集められます。
記事を増やせば増やすほど網羅性が高まり、長期的な資産となるメリットがあります。一方で継続的に執筆するリソースの確保が課題になりがちです。
オウンドメディアについては「【2025年最新版】オウンドメディアの作り方|プロが教える立ち上げ手順と成功のコツ」で詳しく解説しています。
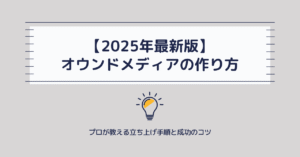
ホワイトペーパー(資料・電子書籍)
より詳細な情報やノウハウをPDFなどの形式で提供する形です。ダウンロード前にリード情報(メールアドレスや会社名など)を取得するケースが多く、見込み顧客の獲得につながりやすい点がポイントです。
深い内容をまとめるため、作成に手間がかかりますが、その分「専門性の高さ」をアピールできます。BtoB商材など、比較検討が長期化しやすい領域との相性が良好です。
コンテンツ制作については「コンテンツ制作とは?目的や種類、効果的な作り方とポイントを徹底解説」も参考にしてください。
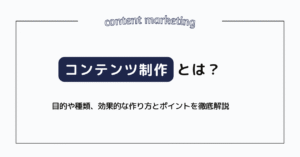
動画やSNS
YouTubeをはじめとした動画プラットフォームでの配信や、Instagram、X(Twitter)などSNSでの情報発信も、コンテンツマーケティングの一部です。ブログやメルマガでは伝わりづらいビジュアル情報や、リアルタイムなコミュニケーションができる利点があります。
たとえばサントリーがYouTube動画を活用してブランドイメージを定着させている事例は有名です。また北欧、暮らしの道具店のように、SNS×ブログ×動画を連動させた複合的なマーケティングも増えています。
Web集客については「Web集客とは?13種類の方法と成功事例、効果的な戦略を徹底解説」で詳しく解説しています。
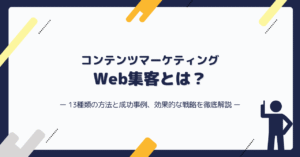
メールマガジン
ユーザーが登録したメールアドレス宛に、最新の記事や新製品情報、イベント告知などを送ります。SNSとは異なり、ユーザーと直接コミュニケーションをとりやすい点が特長です。
新たに記事を更新した際、メールで告知することでリピーターを呼び込みやすくなります。既存顧客との関係維持や追加提案にも有効です。
ウェビナー・オンラインイベント
近年ではオンラインセミナー(ウェビナー)で教育コンテンツを提供し、参加者の興味を高めて購買意欲の形成を促す手法も人気です。質疑応答やアンケートを通じて課題やニーズを把握しやすく、その後の商談につなげられる強みがあります。
コンテンツマーケティングの実践ステップ
基本要素とコンテンツの種類を押さえたうえで、具体的にどのように進めればよいかを見ていきます。おおまかな流れは以下のとおりです。
目的設定
ペルソナ設計
コンテンツ設計
効果測定
具体的な始め方は「コンテンツマーケティングの始め方7ステップ|成果を得るための手順や注意点を詳しく紹介」をご覧ください。

ステップ1:目的設定
まずはコンテンツマーケティングを通じてどのような目標を達成したいか決めます。認知度の向上、リード獲得、ブランディング強化、既存顧客との関係維持など、企業によって狙いはさまざまです。目的を明確にすることで運用方針が固まり、成果測定もしやすくなるでしょう。
アイデア出しについては「コンテンツマーケティングのアイデア出しを成功させる方法|フレームワークや事例を徹底解説」で詳しく解説しています。

ステップ2:ペルソナの設計
目的に合わせて、どんな層にどのような情報を提供すべきかを細かく設定します。性別や年齢だけでなく、購買行動や趣味、課題などをできる限り具体的にイメージします。
たとえばBtoBであれば「課長職だが意思決定権の最終確認は部長。ITシステム導入の責任者で、成果を重視する」といった詳細を盛り込みます。ここで決まったペルソナに対して有益かつ読み応えのあるコンテンツを提供できるよう、次の設計を進めましょう。
企業ブログについては「企業ブログの作り方完全ガイド|目的設定から運用・集客まで徹底解説」も参考にしてください。
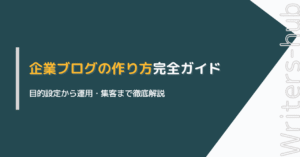
ステップ3:コンテンツ設計
ペルソナが抱える課題や疑問を洗い出し、それらを解決するコンテンツの計画を立てます。キーワードリサーチや競合分析を行い、どのようなテーマで何を伝えるべきかを整理しましょう。
記事設計例(BtoB企業向け)
– メインテーマ:「製造業のコスト削減方法」
– ターゲットペルソナ:製造業の工場長や経営企画担当
– 具体トピック:原価管理の手法、時短につながるシステム導入事例など
こうした明確な設計を行い、ブログ記事やホワイトペーパー、SNSなどを複数組み合わせて発信することで、潜在的な見込み顧客を徐々に顕在化させる効果が期待できます。
ステップ4:効果測定と改善
公開後のコンテンツが実際にどの程度閲覧され、どれだけ問い合わせや資料請求などにつながったかを把握することが重要です。GoogleアナリティクスやSearch Consoleといった解析ツールを用いて、PV数や検索順位、コンバージョン率などをチェックします。
その結果をもとに、改善が必要なページはリライトやキーワードの再検討を行い、継続的に品質を高めましょう。運用を続けることで、コンテンツの蓄積が大きな資産となり長期的に安定した集客と売上につながる可能性が高まります。
効果を高める方法は「コンテンツマーケティングの効果を高める方法とは|成果を導く手順と測定指標も解説」もご覧ください。

運用効果を高めるためのポイント
コンテンツマーケティングは正しい方法で継続すれば大きな成果をもたらしますが、そのためにはいくつかのポイントを意識することが重要です。
改善手法については「コンテンツマーケティングの改善手法と戦略的アプローチ」で詳しく解説しています。
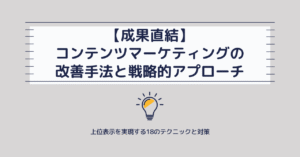
量より質を重視する
検索エンジンのアルゴリズムが「質の高いコンテンツ」を評価する方向に変化しており、むやみに数を増やしても意味がありません。最新の情報、独自の視点、信頼性などがあるコンテンツを丁寧に作成するとよいでしょう。
Googleが公開している「質の高いサイトの作成方法についてのガイダンス」を参考にするのもおすすめです。
質の高いコンテンツについては「結局のところ「質の高いコンテンツ」って何だろう」も参考にしてください。
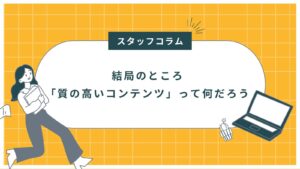
広告臭を出しすぎない
コンテンツマーケティングは有益な情報でユーザーを惹きつける手法です。押し付けがましい広告や宣伝色の強い表現が多いと、ユーザーから敬遠され、検索エンジンの評価も下がりやすくなります。
それよりも読者の課題解決や学びを優先し、自社製品やサービスへの訴求は自然なかたちで盛り込む方が効果的です。
成功法則は「コンテンツマーケティングの成功法則を解説|事例から読み解く成果を上げるポイント」で詳しく解説しています。

内部リンクと情報の網羅性を高める
記事同士を関連付ける内部リンクを整備し、読者が必要な情報をスムーズに発見できるようにすると、サイト全体の評価向上に寄与します。たとえば「コンテンツマーケティングの定義」を読んだユーザーが、「具体的な成功事例」を探しやすい仕組みを作るイメージです。
また1記事だけで完結しないテーマについては複数記事に分割し、網羅的な情報発信をサイト全体で行うとよいでしょう。
チーム体制の確立
コンテンツの継続制作はライターや編集者だけでなく、社内の知見を持つメンバーの協力も欠かせません。専門家のチェックや関係部署との連携があることで、より正確かつ魅力的な情報を発信しやすくなります。
制作から公開、効果測定、リライトまでの流れをチームで管理し、定期的に会議やレビューを行うのが理想です。
コンテンツマーケティング実施時の注意点
コンテンツマーケティングを成功させるには、以下の注意点を意識しておきましょう。
入門的な内容は「コンテンツマーケティング入門|基本的な意味や仕組み・実践のポイントを解説」で詳しく解説しています。

短期的な成果を過度に期待しない
広告のような即効性はあまりありません。しっかりと記事や動画を蓄積し、検索エンジンから評価されるまでには時間が必要です。最低でも半年、可能なら1年以上の継続を念頭に置くとよいでしょう。
コンテンツの定期的な更新を怠らない
一度作った記事や資料を放置すると、情報が古くなるリスクがあります。特に法改正がある分野、技術進歩の速い業界などでは更新が欠かせません。定期的にチェックし、必要に応じて追記や書き換えを行いましょう。
企業ブログの運用は「成功する企業ブログの書き方7ステップ|運用のメリットや注意点も解説」で詳しく解説しています。
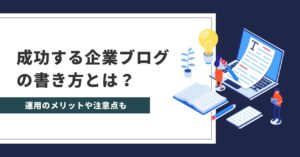
競合との差別化を図る
「コンテンツマーケティング」という言葉自体が広く知られるようになり、競合も同様の戦略をとるケースが増えました。独自の事例、専門家インタビュー、実績データなど、オリジナル要素を活かした差別化が大切です。
差別化については「「他社と似た記事ばかり」を解決するには」をご覧ください。
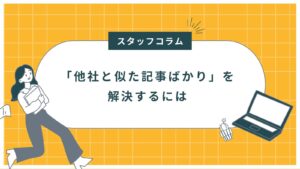
コンテンツマーケティングに関するよくある質問
最後に、企業担当者から寄せられやすい質問に回答します。
コンテンツSEOについては「コンテンツSEOとは?メリットと手順を事例とともに徹底解説」で詳しく解説しています。

どのような成果指標を追えばよいのでしょうか
目標によって変わりますが、一般的には以下がよく用いられます。
- PV数(閲覧数)
- 検索順位
- CV(問い合わせ、資料請求、購入、会員登録など)
- CVR(CV率)
- 被リンク数やSNSシェア数
認知度を高めたいならPV数、リード獲得が目的ならCV率といったように、目的に直結する指標を追うようにすると効果を測定しやすくなります。
効果測定については「コンテンツマーケティングの効果を高める方法とは|成果を導く手順と測定指標も解説」も参考にしてください。

自社で執筆するか外注するか迷っています
それぞれメリット・デメリットがあります。自社で執筆すると専門性やリアルなノウハウを強みにできる一方、品質管理に時間がかかるかもしれません。外注するとリソースを節約でき、プロのライターによる高品質な記事を期待できますが、社内知見を記事化する際はコミュニケーションに労力がかかることもあります。
自社と外部ライターを併用し、記事内容によって書き分ける方法もよく見られます。
コンテンツ制作の外注は「コンテンツ制作外注の費用相場は?おすすめの制作会社についても」で詳しく解説しています。
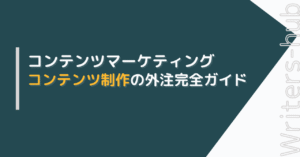
SEOとコンテンツマーケティングの違いは何ですか
SEO(検索エンジン最適化)は、検索結果で上位表示を狙うための施策や考え方を指します。一方、コンテンツマーケティングはコンテンツを用いた顧客との関係構築を広く指す概念です。SEOはコンテンツマーケティングを成功させる手法の一部と捉えるとよいでしょう。
SEOにおけるコンテンツについては「コンテンツSEOとは?メリットと手順を事例とともに徹底解説」をご覧ください。

専門家の力を活用して成果を最大化するには? ~Writers-hubへの相談を
コンテンツマーケティングは、有益な情報を継続して発信する地道な取り組みです。しかし、正しい知識と戦略、そして専門的なライティング技術があれば、長期にわたって安定した集客力とブランド力を得られます。
合同会社Writers-hubは、下記のようなサービスを提供し、数多くの企業のコンテンツマーケティングを支援してきました。
1.SEO記事コンテンツ作成
検索流入を狙った記事の制作をフルサポートします。キーワード選定から校正、CMSへの入稿まで一貫対応が可能です。累計1000本超の記事制作を通じて培ったノウハウを活かし、さまざまなジャンルで成果を出すお手伝いをします。
独自のSEO支援ツールを駆使して検索ユーザーの意図を網羅した質の高い記事構成を作成。単に上位表示を狙うだけでなく、記事内で読者の課題を適切に導き出し自社サービスによる解決を自然に訴求していきます。
2.SEOキーワード戦略設計
サイト全体でどのようなキーワードを攻略すべきかを戦略的に設計します。事前のヒアリングと競合リサーチを丁寧に行い、ビジネス目標に直結するキーワード群を提案します。すべての重要キーワードを漏れなく洗い出し、記事同士をつなぐ内部リンク設計まで一括支援が可能です。
3.SEO記事内製化支援
生成AIの活用や「ハブ式SEOライティング」メソッドを提供し、社内の専門知識を最大限に活かした記事執筆体制の構築をサポートします。記事制作のポイントや品質管理のフローを共有し、運用初期段階の課題を解消します。最新のSEO情報やAIツールの活用法も随時アップデートしてお届けします。
4.課題訴求型Webサイト制作
コンテンツマーケティングでせっかく集客しても、Webサイトの訴求内容や導線が分かりづらいと成果に結びつきません。そこでローカルSEOに強いサイト構造とプロライターが手掛ける効果的な文章設計で、問い合わせや資料請求などを増やすWebサイト制作サービスも提供しています。
5.セミナー・講習会事業
さらに、企業向けのリスキリング支援として、コンテンツSEOやAI活用をテーマとしたセミナーや講習会を実施できます。実務に直結するノウハウを学び、社内全体のスキルを底上げするチャンスです。
「自社に合ったコンテンツマーケティング戦略を立てたい」「SEO対策を強化して検索流入を増やしたい」「継続的に高品質な記事を作りたい」といった課題がある方は、ぜひ合同会社Writers-hubにご相談ください。
貴社が得意とする領域を正しく情報発信し、ビジネス成果の向上につなげるサポートをいたします。
『SEO最強』AIライティングツールで記事を量産したい人は他にいませんか?
3000記事以上の執筆・編集経験を持つSEO専門ライターが、2年間の試行錯誤の末に開発した革新的AIシステム。
- キーワードを入力するだけで5万字超のプロンプトが生成
- ClaudeやChatGPTにコピペするだけで装飾済みの原稿が一発完成
- ライター外注費を最大90%削減可能
-------------------
![]() こんな課題を抱えていませんか?
こんな課題を抱えていませんか?
- 「コンテンツ制作費、もっと安くならないの?」と言われ失注が増えてきた
- ライターとのコミュニケーションコストや管理が大変
- いくらAIツールを試しても本当に「自分が書かなくていいレベル」にならない
-------------------
「一気通貫Pro」があれば解決します!
「立ち上げ4ヶ月で4万PV達成!(上場企業)」
「外注費を90%削減できた。一気通貫Proの原稿が良すぎて6割は時間削減できている(Web制作会社)」
「低コストのSEO記事制作プランを自信を持って提案できるようになり受注率が向上(制作会社)」
他のAIツールとの決定的な違いはこの3点!
- システム会社やSEO会社ではなく現役ライターが開発したから、プロが書いたような「使える」原稿が出力される
- プロンプトを出力するツールなので、生成AIに「ここをもっとこうして」と追加指示で修正も簡単(他のAIツールは修正は人力)
- 生成AIのプランに準じて事実上無制限に記事作成可能(他の多くは月間制限あり)
-------------------
![]() 30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
AIの出力そのままの無料デモ記事の作成も承っています。まずは実際の出力をご確認ください!


