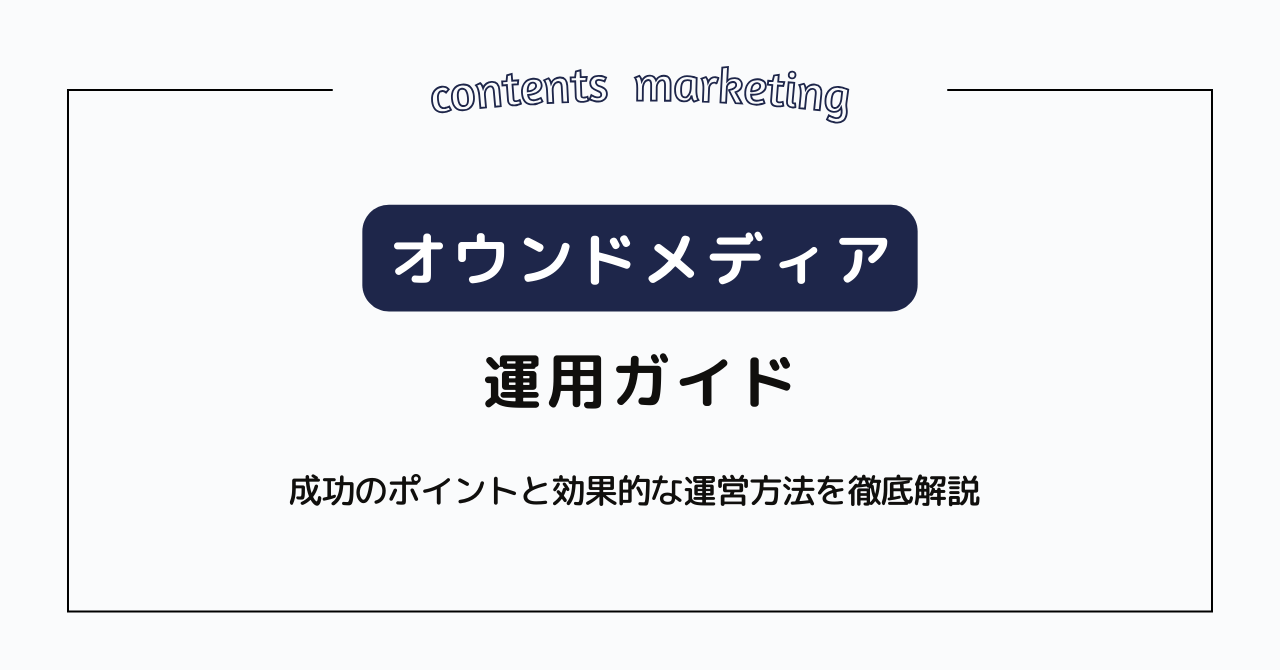
オウンドメディア運用ガイド|成功のポイントと効果的な運営方法を徹底解説
オウンドメディアを運用したいけれど、何から始めたらいいのかわからない。始めてみたものの成果が出ない。そもそも運用体制をどう整えればよいのか悩んでいる——。このような課題を抱える企業は少なくありません。
オウンドメディアは正しく運用することで、リード獲得や認知拡大、採用強化など様々な事業課題の解決につながる可能性を秘めています。しかし、ただ記事を公開するだけでは期待した効果は得られません。
本記事では、オウンドメディア運用の目的から実践的なポイント、効果的な体制づくり、成功事例まで徹底解説します。これからオウンドメディアに取り組む方はもちろん、すでに運用しているけれど成果が出ていない方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
『SEO最強』AIライティングツールで記事を量産したい人は他にいませんか?
3000記事以上の執筆・編集経験を持つSEO専門ライターが、2年間の試行錯誤の末に開発した革新的AIシステム。
- キーワードを入力するだけで5万字超のプロンプトが生成
- ClaudeやChatGPTにコピペするだけで装飾済みの原稿が一発完成
- ライター外注費を最大90%削減可能
-------------------
![]() こんな課題を抱えていませんか?
こんな課題を抱えていませんか?
- 「コンテンツ制作費、もっと安くならないの?」と言われ失注が増えてきた
- ライターとのコミュニケーションコストや管理が大変
- いくらAIツールを試しても本当に「自分が書かなくていいレベル」にならない
-------------------
「一気通貫Pro」があれば解決します!
「立ち上げ4ヶ月で4万PV達成!(上場企業)」
「外注費を90%削減できた。一気通貫Proの原稿が良すぎて6割は時間削減できている(Web制作会社)」
「低コストのSEO記事制作プランを自信を持って提案できるようになり受注率が向上(制作会社)」
他のAIツールとの決定的な違いはこの3点!
- システム会社やSEO会社ではなく現役ライターが開発したから、プロが書いたような「使える」原稿が出力される
- プロンプトを出力するツールなので、生成AIに「ここをもっとこうして」と追加指示で修正も簡単(他のAIツールは修正は人力)
- 生成AIのプランに準じて事実上無制限に記事作成可能(他の多くは月間制限あり)
-------------------
![]() 30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
30社限定のプロトタイプ版参加者募集中!
AIの出力そのままの無料デモ記事の作成も承っています。まずは実際の出力をご確認ください!
オウンドメディアとは
まずは、オウンドメディアの基本的な概念について理解しましょう。ここでは定義から他のメディアとの違いまで解説します。
詳しい作り方は「【2025年最新版】オウンドメディアの作り方|プロが教える立ち上げ手順と成功のコツ」で解説しています。
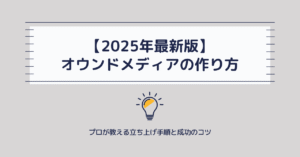
オウンドメディアの定義
オウンドメディア(Owned Media)とは、企業が自社で保有・運営するメディアの総称です。広義には紙のパンフレットや会社案内なども含まれますが、一般的にはWebサイトやブログなどのデジタルメディアを指すことが多いでしょう。
しかし重要なのは、単なる情報発信の場としてではなく、企業の事業課題や採用課題を解決するための戦略的なツールとして捉えることです。「何のために運用するのか」という目的意識が、オウンドメディア成功の第一歩となります。
コンテンツマーケティングについては「コンテンツマーケティングとは?定義からメリット・手法・成功事例まで徹底解説」も参考にしてください。

トリプルメディアにおける位置づけ
マーケティングの文脈では、メディアは「オウンドメディア」「ペイドメディア」「アーンドメディア」の3つに分類されます。これを「トリプルメディア」と呼びます。
- オウンドメディア(Owned Media):自社で所有・運営するメディア
- ペイドメディア(Paid Media):広告など対価を支払って利用するメディア
- アーンドメディア(Earned Media):口コミやSNSでのシェアなど、第三者が自発的に広めてくれるメディア
この中でオウンドメディアは、自社でコントロールできる唯一のメディアです。コンテンツの蓄積によって長期的な資産となる点や、他のメディアへの導線として機能する点が大きな特徴です。
企業の情報発信については「企業の情報発信方法7選|目的やメリット・炎上しないための注意点も解説」で詳しく解説しています。

オウンドメディアとコーポレートサイトの違い
「オウンドメディア」と「コーポレートサイト」は混同されがちですが、目的や特徴に違いがあります。以下に主な違いをまとめました。
| オウンドメディア | コーポレートサイト | |
| 目的 | 顧客の課題解決、情報提供、リード獲得など | 会社情報や商品・サービス情報の提供 |
| コンテンツ | ユーザーの悩みや関心に応えるコンテンツ | 自社や商品・サービスの紹介 |
| 更新頻度 | 定期的な更新が基本 | 情報変更時の更新が中心 |
| 訴求方法 | ユーザーの課題解決を通じた間接的アプローチ | 商品・サービスの直接的アピール |
| 設計思想 | ユーザー中心(ユーザーファースト) | 企業中心(カンパニーファースト) |
両者の違いを理解したうえで、それぞれの特性を活かした運用が重要です。最近では、コーポレートサイトとオウンドメディアを連携させる「ハイブリッド型」の展開も増えています。
オウンドメディア運用の目的
オウンドメディアを効果的に運用するには、目的を明確にすることが大切です。ここでは、一般的なオウンドメディア運用の目的を解説します。
Web集客については「Web集客とは?13種類の方法と成功事例、効果的な戦略を徹底解説」で詳しく解説しています。
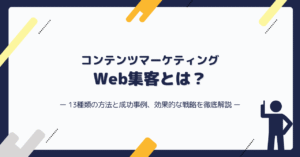
リード獲得
BtoB企業でもっとも多いオウンドメディアの運用目的が「リード獲得」です。見込み顧客が抱える課題や関心事に対して有益な情報を提供し、その過程で自社製品・サービスへの導線を設計します。
例えば、人事システム会社なら「採用難時代の人材確保法」といったコンテンツを通じて課題を抱える企業の興味を引き、自然な流れで自社ソリューションを紹介することができます。
リード獲得を目的とする場合は、コンバージョンポイントの設計と導線づくりが特に重要となります。問い合わせフォームやホワイトペーパーのダウンロード、セミナー申し込みなど、読者の状況に合わせた適切なアクションを設計しましょう。
認知拡大とブランディング
企業や商品・サービスの認知を高めることも、オウンドメディア運用の重要な目的です。まだあまり知られていない分野や、新規事業、新商品の立ち上げ時などに特に効果的です。
認知拡大を目的とする場合は、ターゲットユーザーが検索しそうなキーワードを意識したコンテンツ設計や、SNSでシェアされやすいコンテンツづくりが重要となります。
また、「この領域についてはこの企業に聞けば間違いない」というブランディング効果も、オウンドメディアの大きなメリットです。自社の専門性や価値観を体現するコンテンツを継続的に発信することで、ユーザーの信頼構築につなげることができます。
コンテンツマーケティングの重要性は「コンテンツマーケティングの重要性とは?目的やメリット、成功へのステップを徹底解説」で詳しく解説しています。

SEO強化・検索順位向上
オウンドメディアのコンテンツ蓄積は、SEO(検索エンジン最適化)の強化にもつながります。専門性の高いコンテンツを継続的に発信することで、検索エンジンからの評価向上が期待できます。
コーポレートサイトだけでは対応しきれないキーワードをオウンドメディアでカバーすることで、より多くの検索クエリに対応できるようになります。これにより、自社サイト全体の流入増加につながる効果が期待できます。
SEOの基礎知識は「【2025年最新】SEOとは?初心者でもわかる基本と効果的な対策法」をご覧ください。
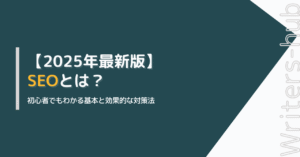
採用力強化
人材採用を強化する目的でオウンドメディアを運用するケースも増えています。社風や働き方、社員の声などを発信することで、企業の魅力を伝え、採用活動を支援します。
採用サイトと異なり、オウンドメディアでは日常の業務内容や社員の本音、企業文化などをより自然な形で伝えられる点がメリットです。求職者は採用サイトよりも、こうした「リアルな情報」に魅力を感じる傾向があります。
企業ブログの活用は「企業ブログの作り方完全ガイド|目的設定から運用・集客まで徹底解説」で詳しく解説しています。
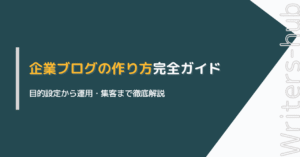
マネタイズ
オウンドメディア自体を収益源とする「マネタイズ」も運用目的の一つです。広告収入やアフィリエイト、有料会員制などの方法で収益化を図ります。
ただし、マネタイズを主目的とする場合は、コンテンツの質と量の両面で高いレベルが求められる点に注意が必要です。また、自社の事業目的とバランスを取りながら収益化を進めることが重要です。
成功するオウンドメディア運用の5つのポイント
オウンドメディアを成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、成功するオウンドメディア運用に欠かせない5つのポイントを解説します。
オウンドメディア運用の5つのポイント 1 明確な目的設定 2 適切な成果指標の設定 3 戦略の設計 4 実行体制の構築 5 継続的な評価と改善成功法則については「コンテンツマーケティングの成功法則を解説|事例から読み解く成果を上げるポイント」も参考にしてください。

1. 運用目的の明確化
オウンドメディア運用の第一歩は、なぜそのメディアを運用するのかという目的の明確化です。前述したリード獲得、認知拡大、ブランディング、採用強化などの目的を明確にしないまま運用を始めると、方向性が定まらず効果測定も困難になります。
目的を明確にする際は、以下の点に注意しましょう。
- 抽象的な目的ではなく、具体的に何を達成したいのかを明確にする
- 複数の目的がある場合は優先順位をつける
- 目的達成までの大まかな道筋をイメージする
- 目的が会社の事業目標とつながっているか確認する
目的が明確であれば、コンテンツの方向性やターゲット設定、評価指標なども自ずと定まってきます。
コンテンツマーケティング戦略は「コンテンツマーケティング戦略の立て方を徹底解説|成果を伸ばす具体的なステップ」で詳しく解説しています。

2. 適切な成果指標の設定
目的を定めたら、次はその達成度を測るための成果指標(KPI)を設定します。目的によって重視すべき指標は異なります。
例えば、以下のような目的別の指標が考えられます。
| 目的 | 主な成果指標 |
| リード獲得 | 問い合わせ数、資料ダウンロード数、セミナー申込数など |
| 認知拡大 | PV数、UU数、滞在時間、SNSシェア数など |
| ブランディング | 直接訪問数、ブランド検索数、メディア掲載数など |
| SEO強化 | オーガニック流入数、キーワードランキング、被リンク数など |
| 採用強化 | 採用応募数、採用サイトからの流入数など |
重要なのは、「PV数を増やす」といった漠然とした指標ではなく、最終的な事業成果につながる指標を選ぶことです。また、指標は定期的に見直し、必要に応じて調整することも大切です。
効果測定については「コンテンツマーケティングの効果を高める方法とは|成果を導く手順と測定指標も解説」をご覧ください。

3. 戦略の設計
目的と成果指標が決まったら、それを達成するための戦略を設計します。オウンドメディアの戦略設計には、以下の要素が含まれます。
- ターゲット(ペルソナ)設定:誰に向けて情報を発信するのかを明確にする
- コンテンツ戦略:どのようなテーマ・トピックで情報を発信するか計画する
- キーワード戦略:ターゲットが検索しそうなキーワードを洗い出し、優先順位をつける
- 差別化戦略:競合メディアとの差別化ポイントを明確にする
- 導線設計:メディア内での回遊や最終的なコンバージョンへの誘導経路を設計する
戦略設計の段階では、「理想的なユーザージャーニー」をイメージすることが重要です。ユーザーがどのようにメディアに訪れ、どのような情報を求め、最終的にどのようなアクションにつなげたいのかを具体的に描きましょう。
企画立案については「成功するコンテンツマーケティングの企画立案の作り方|企画書を作る際のポイントも」で詳しく解説しています。
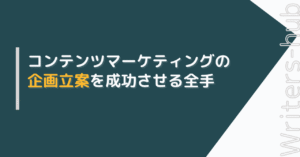
4. 実行体制の構築
オウンドメディアの戦略を実行に移すためには、適切な運用体制の構築が不可欠です。この点については後ほど詳しく解説しますが、主に以下の要素が重要となります。
- 責任者・意思決定者の明確化
- コンテンツ制作フローの確立
- 必要なリソース(人材・予算・時間)の確保
- 社内外の協力体制の構築
オウンドメディアの運用は継続が命です。一時的なブームや担当者の熱意だけに頼らない、持続可能な体制づくりを心がけましょう。
コンテンツ制作の外注は「コンテンツ制作外注の費用相場は?おすすめの制作会社についても」も参考にしてください。
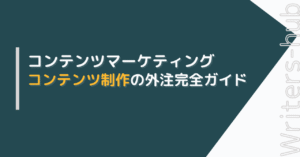
5. 継続的な評価と改善
オウンドメディアは運用開始して終わりではなく、継続的な評価と改善が成功のカギとなります。定期的に以下のサイクルを回すことで、メディアの価値を高めていきましょう。
- データ分析:アクセス解析やコンバージョン率などのデータを定期的に確認
- 課題抽出:データから見える課題や改善点を洗い出す
- 改善施策の実施:コンテンツの追加・修正、UI/UXの改善、導線の最適化など
- 効果検証:改善施策の効果を測定し、次のアクションにつなげる
評価・改善のサイクルは、週次・月次・四半期など、メディアの規模や目的に応じて適切な頻度を設定しましょう。
コンテンツの改善手法は「コンテンツマーケティングの改善手法と戦略的アプローチ」で詳しく解説しています。
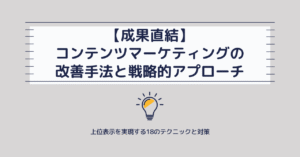
オウンドメディアの効果的な運用体制
オウンドメディアの成否を左右する重要な要素が「運用体制」です。ここでは、効果的な運用体制の作り方について解説します。
コンテンツ制作については「コンテンツ制作とは?目的や種類、効果的な作り方とポイントを徹底解説」で詳しく解説しています。
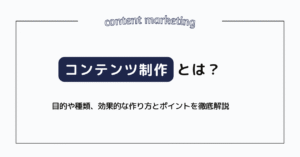
社内運営と外部委託の選択
オウンドメディアの運用体制は、大きく「社内運営」と「外部委託」の2つに分けられます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社に最適な方法を選びましょう。
| メリット | デメリット | |
| 社内運営 | ・自社の強みや専門性を活かせる ・ノウハウが社内に蓄積される ・スピーディーな意思決定が可能 ・コスト管理がしやすい | ・専門知識やスキルの習得に時間がかかる ・リソース確保が難しい場合がある ・客観的視点が不足しがち |
| 外部委託 | ・専門的なノウハウをすぐに活用できる ・社内リソースを節約できる ・客観的な視点が入る ・短期間で結果が期待できる | ・コミュニケーションコストがかかる ・自社の強みや専門性が伝わりにくい ・継続的なコストがかかる |
どちらか一方に限定する必要はなく、「企画・戦略は社内で、制作は外部委託」「立ち上げ時は外部の力を借り、徐々に内製化」といった組み合わせも有効です。自社のリソースや目的に合わせて最適な形を選びましょう。
ライターについては「「良いライターがいない」の解決策を考える」をご覧ください。
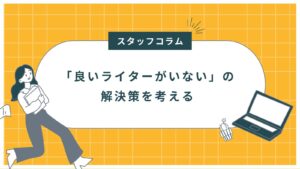
理想的な運用体制の構築
オウンドメディアの理想的な運用体制には、以下のような役割が必要です。
- PM(プロジェクトマネージャー):全体の進行管理や予算管理を担当
- コンテンツディレクター:コンテンツ戦略の立案と実行管理を担当
- 記事ディレクター:個別記事の企画立案と品質管理を担当
- ライター:実際の記事執筆を担当
- マーケティングディレクター:集客施策やSEO対策を担当
- 施策実行担当:SNS運用やメルマガ配信などを担当
大規模なメディアならこれらの役割を別々の担当者が担いますが、小規模な場合は1人が複数の役割を兼任することも多いでしょう。重要なのは、各役割の責任範囲を明確にし、連携がスムーズに行える体制を作ることです。
コンテンツマーケティングの基礎は「コンテンツマーケティングの基礎知識を総まとめ|やり方から成果につなげる方法まで徹底解説」で詳しく解説しています。

社内体制を整えるポイント
社内での運用体制を整える際のポイントとして、以下の点に注意しましょう。
- 責任者と担当部署の明確化
オウンドメディアの責任者と担当部署を明確にしましょう。マーケティング部門か広報部門か、あるいは専門チームを作るのか、自社に合った形を選びます。 - 人員と予算の確保
継続的な運用に必要な人員と予算を確保しましょう。特に立ち上げ期は想定以上のリソースが必要になることがあります。 - オウンドメディアの必要性の共有
社内全体にオウンドメディアの目的や重要性を伝え、理解と協力を得ることが大切です。 - クオリティチェック体制の確立
記事の品質を担保するためのチェック体制を確立しましょう。専門知識や事実確認、表現の適切さなどを複数の目でチェックする仕組みが重要です。
オウンドメディアの運用は長期的な取り組みです。一時的な熱意に頼るのではなく、持続可能な体制づくりを心がけましょう。
外部委託する際のポイント
オウンドメディアの運用を外部に委託する場合は、以下のポイントに注意しましょう。
- 委託先の選定基準を明確にする
実績、専門分野、提供サービスの範囲、費用などを比較検討しましょう。 - 自社の強みや専門性を伝える
委託先に自社の強みや専門性を十分に理解してもらうことが重要です。定期的なコミュニケーションを心がけましょう。 - 明確なゴールと評価指標を共有する
何を目的とし、どのような成果を期待しているのかを明確に伝えましょう。 - 自社でのチェック体制を整える
外部委託であっても、最終的な責任は自社にあります。内容確認のための体制を整えましょう。
外部委託の形態も様々です。「完全外部委託」「企画だけ委託」「制作だけ委託」など、自社の状況に合わせて最適な形を選びましょう。
オウンドメディア運用に必要なコンテンツ制作の考え方
オウンドメディアの価値を左右するのは、そこで提供されるコンテンツです。ここでは、効果的なコンテンツ制作の考え方について解説します。
Web記事の書き方は「Web記事の書き方完全ガイド|初心者からプロまで使える7つのステップとコツ」も参考にしてください。
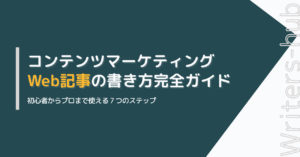
コンテンツSEOで重要なキーワード設計
オウンドメディアで多くの読者を獲得するためには、SEO(検索エンジン最適化)の視点が欠かせません。その中でも特に重要なのが「キーワード設計」です。
キーワード設計のステップは以下の通りです。
- ターゲットユーザーの検索行動を想定
ターゲットとなるユーザーがどのような言葉で検索するか想定します。 - 関連キーワードの洗い出し
キーワードプランナーやラッコキーワードなどのツールを使って関連キーワードを洗い出します。 - キーワードの分類と優先順位付け
検索ボリュームや競合性、商品との関連性などを考慮して優先順位をつけます。 - コンテンツ計画への落とし込み
優先度の高いキーワードから順にコンテンツ計画に落とし込みます。
キーワード設計では、「検索ボリューム」だけでなく「ユーザーの検索意図」を理解することが重要です。同じキーワードでも、情報を求めている人と商品を探している人では求める内容が異なります。
キーワード選定については「「え?そんな簡単なの?」SEO初心者でも使える、キーワード選定のマル秘テクニック」で詳しく解説しています。
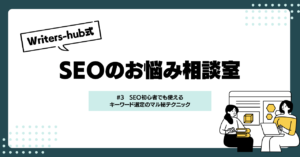
良質なコンテンツを生み出す
SEOで上位表示されるためには、ユーザーにとって価値のある良質なコンテンツを提供することが不可欠です。良質なコンテンツの条件としては、以下の点が挙げられます。
- ユーザーの課題や疑問に答えている
ユーザーが知りたい情報や解決したい課題に的確に応えるコンテンツを提供しましょう。 - 独自の視点や価値がある
他のサイトにはない独自の視点や専門的な知見を加えることで、コンテンツに価値を持たせましょう。 - 分かりやすく整理されている
読みやすい文章構成や適切な見出し、図表の活用など、情報が整理されていることも重要です。 - 最新かつ正確な情報を提供している
古い情報や誤った情報は読者の信頼を損ねます。情報の正確性と鮮度を保ちましょう。
良質なコンテンツを継続的に生み出すためには、制作プロセスの標準化も重要です。企画、リサーチ、執筆、チェック、公開という流れを明確にし、効率的に質の高いコンテンツを生み出せる体制を整えましょう。
検索で上位表示させるために、どれくらいの文字数が必要か?
SEO記事の文字数について「何文字書けばいいのか」という質問をよく受けます。結論から言えば、文字数に絶対的な基準はなく、キーワードや競合状況によって異なります。
一般的には、競合記事の文字数を参考にしつつ、「ユーザーの疑問に十分に答えられる量」を目安とするとよいでしょう。同じテーマでも、「初心者向けの基礎解説」なら3,000字程度、「専門的な深掘り記事」なら8,000字以上必要になるケースもあります。
重要なのは「量」よりも「質」です。必要な情報をしっかり網羅し、余計な内容で水増ししないようにしましょう。
SEO記事の書き方は「SEO記事の書き方完全ガイド|上位表示を実現する18のテクニックと対策」をご覧ください。
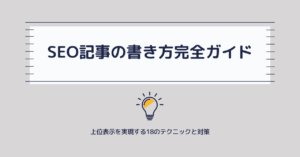
公開後も、コンテンツを育て、運用する
オウンドメディアのコンテンツは、公開したら終わりではなく、継続的に「育てる」視点が重要です。以下のようなアプローチで、コンテンツの価値を高めていきましょう。
- 定期的な更新・リライト
古くなった情報の更新や、より詳しい情報の追加など、定期的なリライトを行いましょう。 - ユーザーの反応を確認
アクセス数やCVR、滞在時間など、ユーザーの反応からコンテンツの評価を確認し、改善に活かしましょう。 - 関連コンテンツとの連携
新しく公開したコンテンツとの相互リンクなど、コンテンツ間の連携を強化しましょう。 - 拡散・再配信
SNSでの再配信やメルマガでの紹介など、コンテンツの露出機会を増やす工夫も重要です。
特にSEOの観点では、競合記事の動向や検索アルゴリズムの変化に合わせて、定期的に記事を見直す習慣をつけることが大切です。
ブログの更新頻度は「ブログの最適な更新頻度とは?SEO効果と成功戦略を徹底解説」で詳しく解説しています。
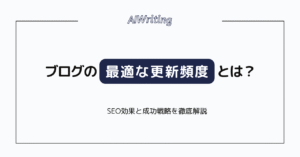
オウンドメディアの成功事例
ここでは、実際に成果を上げているオウンドメディアの事例を紹介し、そこから学べるポイントを解説します。
コンテンツマーケティングの成功事例は「コンテンツマーケティングの成功法則を解説|事例から読み解く成果を上げるポイント」も参考にしてください。

BtoB企業の成功事例
ウィルオブ・ワーク|リード獲得型
人材サービス会社のウィルオブ・ワークが運営する「採用ノウハウ」は、採用担当者向けの情報を提供するオウンドメディアです。採用に関する悩みや課題に対するソリューションを提供することで、リード獲得につなげています。
成功のポイント:
- 採用担当者が抱える具体的な課題に焦点を当てたコンテンツ
- 実践的なノウハウや事例を豊富に提供
- 無料ダウンロード資料をリード獲得のきっかけに活用
サイボウズ式|ブランディング・認知拡大型
グループウェア開発会社サイボウズが運営する「サイボウズ式」は、働き方や組織運営に関する情報を発信するメディアです。業務効率化やリモートワークなど幅広いテーマを扱い、企業理念の「チームワークあふれる社会を創る」を体現しています。
成功のポイント:
- 自社の理念や価値観を反映したコンテンツ
- 社員や外部専門家の知見を活かした深い洞察
- 自社サービスの直接的な宣伝ではなく、価値ある情報提供に焦点
BtoC企業の成功事例
ビギナーズ|ユーザー獲得型
株式会社カインズが運営する「ビギナーズ」は、DIYや園芸、掃除などの暮らしに関する情報を提供するメディアです。初心者向けのノウハウを中心に、自社商品の活用法も交えたコンテンツを展開しています。
成功のポイント:
- 初心者でも取り組みやすい実用的なコンテンツ
- 豊富な写真や図解で分かりやすく解説
- 自然な形で自社商品を紹介し、ECサイトへの導線を設計
メルカン|採用・ブランディング型
株式会社メルカリが運営する「mercan(メルカン)」は、企業文化や働き方、社員の声などを発信するメディアです。採用強化とブランディングを目的に、会社の内側から見た姿を伝えています。
成功のポイント:
- 社員のリアルな声や日常を伝えるコンテンツ
- 企業理念や価値観を具体的なエピソードで表現
- エンジニアやデザイナーなど職種別の情報も充実
事例から学ぶ成功のポイント
これらの成功事例から学べる共通のポイントをまとめると、以下のようになります。
- 目的から成果を定義する
成功している企業は、「なぜオウンドメディアを運用するのか」という目的からブレずに、具体的な成果指標を設定しています。 - フェーズを分けて戦略を立てる
立ち上げ期、成長期、安定期など、フェーズによって適切な戦略が異なることを理解し、段階的にアプローチしています。 - リソースの選択と集中
すべてを完璧にするのではなく、目的達成に最も効果的な領域にリソースを集中投下しています。 - ユーザーの課題解決を最優先
自社アピールよりも、ユーザーが抱える課題や疑問に真摯に向き合うコンテンツを提供しています。 - 継続的な改善と発信
一度立ち上げて終わりではなく、データ分析に基づく継続的な改善と発信を行っています。
成功するオウンドメディアに「魔法の杖」はありません。地道な努力の積み重ねが大きな成果につながります。
オウンドメディア運用の始め方
これからオウンドメディアを始める方に向けて、具体的な進め方を解説します。
コンテンツマーケティングの始め方は「コンテンツマーケティングの始め方7ステップ|成果を得るための手順や注意点を詳しく紹介」で詳しく解説しています。

1. 目的の明確化
まずは「なぜオウンドメディアを始めるのか」という目的を明確にしましょう。リード獲得、認知拡大、SEO強化、採用強化など、主要な目的を決め、それに基づいて戦略を立てます。
目的を定める際は、以下の点を意識しましょう。
- 自社の事業目標とどのようにつながるのか
- 具体的にどのような成果を期待するのか
- 目的達成までの大まかなタイムラインはどうなるか
2. ターゲットの設定
誰に向けて情報を発信するのかを明確にします。年齢、性別、職業、興味関心、課題、情報収集行動など、できるだけ具体的なペルソナを設定しましょう。
ペルソナ設定では、以下のような情報を整理します。
- 基本情報:年齢、性別、職業、家族構成など
- 行動特性:情報収集の方法、休日の過ごし方、購買行動など
- 課題・悩み:現在抱えている課題や悩み
- ニーズ:解決したい問題や得たい情報
3. コンセプト設定
メディアの方向性やテーマ、差別化ポイントなどを決めるコンセプト設定を行います。「何を」「どのように」伝えるのかを明確にしましょう。
コンセプト設定では、以下の要素を検討します。
- メディアのテーマ:取り扱う主要なトピックや分野
- 提供価値:読者にどのような価値を提供するか
- トーン&マナー:文体や表現のスタイル
- 差別化ポイント:他メディアとの違い
4. 運用体制の構築
誰がどのような役割を担うのか、運用体制を構築します。社内リソースだけで運用するのか、外部の力を借りるのか、最適な形を選びましょう。
運用体制構築では、以下のポイントを押さえましょう。
- 役割分担:企画、執筆、編集、公開、分析など各工程の担当者
- ワークフロー:企画から公開までの流れと所要時間
- 公開ペース:どのくらいの頻度でコンテンツを公開するか
- 予算・リソース:必要な予算と人的リソース
5. サイト・コンテンツ制作
メディアのデザインやシステム構築、初期コンテンツの制作を行います。ユーザー体験を重視したデザインと、目的達成につながるコンテンツ設計が重要です。
サイト・コンテンツ制作では、以下の要素に注目しましょう。
- UI/UXデザイン:使いやすさと見た目の良さのバランス
- コンテンツ構成:カテゴリ設計や記事同士の関連づけ
- SEO対策:検索エンジンからの流入を増やす工夫
- コンバージョン設計:問い合わせや資料請求などへの誘導
6. 配信・効果測定
公開したコンテンツの効果を測定し、改善につなげるサイクルを確立します。アクセス解析やコンバージョン率など、目的に応じた指標を設定しましょう。
効果測定では、以下のような指標を活用します。
- トラフィック指標:PV数、UU数、滞在時間、直帰率など
- 流入経路:自然検索、SNS、参照元など
- エンゲージメント:シェア数、コメント数、読了率など
- コンバージョン:問い合わせ数、資料請求数、購入数など
オウンドメディアは「作って終わり」ではなく、「運用し続けること」で価値が高まります。定期的なデータ分析と改善のサイクルを確立し、長期的な視点で育てていきましょう。
オウンドメディア運用の注意点と失敗しないためのコツ
オウンドメディアの運用にはいくつかの注意点があります。よくある失敗パターンを知り、事前に対策を講じることで、よりスムーズな運用が可能になるでしょう。
効果的なSEO対策は「【2025年最新版】初心者でもできるSEOのやり方完全ガイド」をご覧ください。
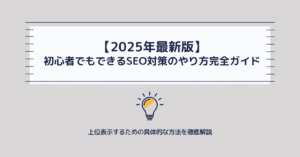
成果が出るまでの時間を理解する
オウンドメディアは、すぐに成果が出る施策ではありません。通常、SEOの効果が表れるまでには数ヶ月、本格的な成果が出るまでには半年から1年以上かかることも珍しくありません。
短期的な視点で成果を求めると、途中で挫折してしまう可能性があります。長期的な視点を持ち、継続的な運用を前提とした計画を立てましょう。
成果までの時間を短縮するための工夫としては、以下のようなことが考えられます。
- 初期段階からSNSや既存顧客へのメール配信などを併用する
- 競合が少ないロングテールキーワードから攻める
- 関連サイトからの被リンクを獲得する取り組みを行う
運用にコストや手間がかかることを理解する
オウンドメディアの運用には、継続的なコストと手間がかかります。質の高いコンテンツの制作や、定期的な更新、効果測定と改善など、想像以上のリソースが必要になることがあります。
運用を始める前に、必要なリソースを現実的に見積もり、持続可能な体制を整えることが重要です。特に人的リソースの確保は、オウンドメディア成功の鍵となります。
リソース面での注意点は以下の通りです。
- 兼任担当者だけでは継続が難しい場合が多い
- 外部委託の場合も社内の窓口担当者は必要
- 初期投資だけでなく、継続的な運用コストを見込む
目的とのズレを防ぐ
運用を続けるうちに、当初の目的からズレてしまうケースは少なくありません。「PVが増えた」「記事数が増えた」といった中間指標ばかりに目を向け、本来の目的である「リード獲得」や「認知拡大」などを見失わないように注意しましょう。
目的とのズレを防ぐためには、以下のような取り組みが効果的です。
- 定期的に目的と現状のギャップを確認する
- 中間指標と最終指標の両方をバランスよく見る
- 目的達成に寄与しない活動は思い切って見直す
行動量なくしてメディア運営の成功はない
オウンドメディアの成功には、継続的な行動量が不可欠です。質の高いコンテンツを継続的に発信し、データを分析し、改善を重ねる。この地道な作業の積み重ねが、最終的な成果につながります。
「やるべきことがわかっていても手が回らない」という状況に陥らないよう、リソースの確保と優先順位付けを徹底しましょう。特に初期段階では、完璧を目指すよりも「まずは動かす」ことを優先するとうまくいくことが多いです。
目的なきオウンドメディアは、やらないほうがよい
「他社がやっているから」「SEOに良いと聞いたから」といった曖昧な理由でオウンドメディアを始めると、途中で挫折する可能性が高まります。明確な目的と戦略がない状態でのオウンドメディア運用は、リソースの無駄遣いになりかねません。
オウンドメディアを始める前に、以下の問いに答えられるかチェックしましょう。
- なぜオウンドメディアを運用するのか?
- オウンドメディアでどのような成果を目指すのか?
- その成果はどのように事業目標につながるのか?
- 必要なリソースを継続的に確保できるか?
これらの問いに明確に答えられない場合は、まずは目的や戦略の再検討から始めることをおすすめします。
まとめ:オウンドメディアを成功させるためのカギ
本記事では、オウンドメディア運用の目的から実践的なポイント、効果的な体制づくり、成功事例までを解説してきました。最後に、オウンドメディアを成功させるためのカギをまとめます。
- 明確な目的設定
何のためにオウンドメディアを運用するのか、事業目標とどうつながるのかを明確にしましょう。 - ターゲットへの価値提供
自社のアピールよりも、ターゲットユーザーの課題解決や価値提供を優先しましょう。 - 継続的な運用体制
長期的な視点で、継続可能な運用体制を構築しましょう。 - 質の高いコンテンツ
ユーザーの役に立つ、質の高いコンテンツを提供し続けましょう。 - データに基づく改善
定期的にデータを分析し、継続的な改善を行いましょう。
オウンドメディア運用は一朝一夕で成果が出るものではありませんが、継続的な取り組みによって、競合他社との差別化や長期的な集客資産の構築につながります。目的を見失わず、地道な努力を積み重ねることが、最終的な成功への道です。
また、オウンドメディアの運用に不安や課題を感じる場合は、専門家への相談も検討しましょう。プロのノウハウを活用することで、より効率的かつ効果的な運用が可能になります。
オウンドメディアの戦略設計や運用は、プロにご相談ください
オウンドメディアの立ち上げや運用に悩んでいる方は、SEOライティングのプロ集団である合同会社Writers-hubにご相談ください。
Writers-hubでは、SEO記事コンテンツ作成やSEOキーワード戦略設計のサービスを提供しており、累計1000本以上の記事制作実績と独自のSEO支援ツールを活用した質の高いコンテンツ制作をサポートします。
特に以下のようなお悩みをお持ちの方におすすめです。
- オウンドメディアの立ち上げ方がわからない
- SEOに強い記事の書き方がわからない
- コンテンツを作っても成果につながらない
- 社内リソースだけでの運用が難しい
- 社内でのSEOライティング体制を構築したい
Writers-hubは単なる記事制作だけでなく、キーワード選定から記事構成、執筆、効果測定まで一貫してサポート。さらに、コンバージョンを意識した記事設計により、読者を自然に自社サービスへと導く仕組みづくりもサポートします。
またSEO記事内製化支援サービスでは、社員による記事執筆体制の構築や、ChatGPTなどの生成AIを活用したコンテンツ制作のノウハウ提供も行っています。
オウンドメディアの成功には、戦略的なアプローチと専門的なノウハウが不可欠です。Writers-hubのサービスを活用し、効果的なオウンドメディア運用を実現しましょう。


